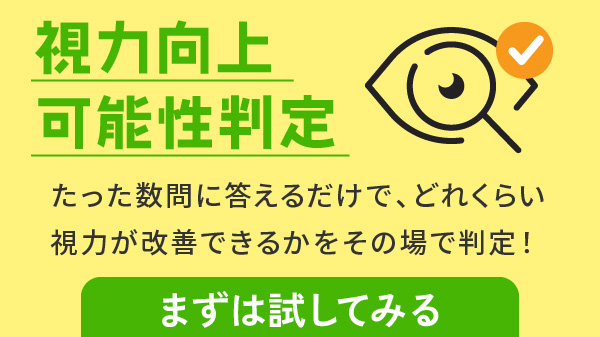※本記事は主に「小学生・A/B判定」向けです。C/D判定・大人の近視・老眼の方向け記事も順次公開予定—あなたに合う対策をわかりやすくご案内します。
小学生なのに“疲れ目”?—タブレット学習時代の新しい普通

学校の視力検査(学校健診の視力検査・いわゆる「学校検眼」)でA/B—「ひと安心」と思ったら、ちょっと待って。
今の小学生は、親の世代とは学び方が違います。タブレットやPCが“毎日の勉強道具”。とくにタブレット学習での疲れ目に心当たりがあるなら要チェック。30cm未満の至近距離×連続使用は、子どもの調節緊張(=仮性近視)を招き、夕方になると「黒板がにじむ」「ピントが合いにくい」など見え方の揺らぎが起こります。つまり、A/Bでも“今は見えているだけ”かもしれません。
かんたんチェック
- タブレットや本に顔をすぐ近づけて見ている(30cm未満)
- 30分以上続けて見てしまうことが多い
- 夕方はぼやけやすい/目が重い、休憩すると少し改善する
いくつか当てはまれば、調節の“こり”が疑われます。
A判定でも近視予防が必要な理由—眼軸が伸びると上がる“目のリスク”
 真性近視とは、眼軸(目の奥行き)が伸びてしまうこと。いったん伸びた眼軸は基本的に元には戻りません。だからこそ、いまの小さな習慣と定期チェックが将来の安心につながります。
真性近視とは、眼軸(目の奥行き)が伸びてしまうこと。いったん伸びた眼軸は基本的に元には戻りません。だからこそ、いまの小さな習慣と定期チェックが将来の安心につながります。
メガネやコンタクトはあくまで“見え方を整える”道具で、進行そのもの(眼軸の伸び)を抑える取り組みは別に必要です。
『日常に困らない=近視は進んでいない』とは限らない——この一点だけ覚えておいてください。
- 黄斑の萎縮・出血(病的近視):視力の土台が傷むことがある
- 網膜剥離:若い世代でも起こり得るため、早めの対策が安心です
- 緑内障の発症リスク上昇:強い近視ほど可能性が高い
- 白内障が早まり手術が難しくなること:眼軸が長いほど、手術計画が複雑になりやすい
眼軸が伸びるほど可能性は高まります。だからA/Bの今こそ、生活とケアでしっかりブレーキをかけていきましょう。
数字でわかる:眼軸が伸びると増えるリスク
- 近視が1D(−1.00)進むごとに、特定の網膜疾患リスクが最大23%上昇との報告(国内医療ニュース要約)。
- 緑内障:軽度近視でも約4倍かかりやすい(日本眼科医会の患者向け解説)。
- 網膜剥離:強い近視で約13〜21.5倍になりやすいとする解説がある(近視情報サイトの日本語記事)。
- 強度近視の目安:眼軸長26.5mm以上または−6.00D超(国内眼科解説)。
虫歯と同じ。予防&早期対処が肝心—家庭×眼科の二本柱

視力を守る4つの習慣
小学生の近視予防は、距離・休憩・屋外・睡眠の4つが土台です。
- 屋外2時間/日:外で体を動かす時間を習慣化
- ねらい:自然光の下で過ごし、遠くを見る機会を増やす(屋外の明るさ+遠方視)
- やり方:分割OK(例:20〜30分×4回)。安全や天候で難しい日は、窓の外の遠くを見る/ベランダや屋根付きスペースなども活用
- ホームワックは室内で“遠くを見ながら”行えるため、屋外が取りづらい日の補完に。※屋外2時間の代替ではなく上乗せと考える
- 距離30–40cm以上(目とタブレット/本/ノート/ディスプレイとの距離)
- 姿勢:背すじを伸ばし、足裏は床にしっかりつける、ひざは90°、ひじは机と水平(椅子の高さや足台で調整)
- 画面位置:目線より少し下、タブレットは10〜20°前傾(反射が少ない角度)
- 明るさ:手元が暗い時は、デスクライトで明るさを補う
- こまめな目の休憩:5分〜30分見たら5秒~30秒遠くを見るハーフタイムの習慣化
- 十分な睡眠:育ちざかりの目に不可欠

眼科で“見える化”
- 正確な度数検査(目薬でピント調節を一時オフにして測る)+眼軸長(AL)を測る
- 6か月ごとにALと屈折度数(SE)のグラフ化で、変化を“数値で見える化”
ミニコラム:何で進行を判断する?(眼軸長 vs 屈折度数)
- 眼軸長(AL)=目そのものの“長さ”。日内変動が少なく、オルソ等の角膜形状変化の影響も受けにくいので進行判定の軸に向きます。学童期の自然伸長はおおむね年間0.2–0.3mm。0.3–0.4mm/年以上ならブレーキ強化を検討。
- 屈折度数(SE)=“見え方の結果”。調節や角膜形状の影響を受けやすいため、必ず「正確な度数検査(目薬で調節を一時オフ)」で評価を。−0.5D/年以上の進行は要注意。単回値ではなくトレンドで判断。
- 治療中の見方:オルソではSEは良く見えてもALが伸びていれば進行中。DIMS/多焦点CLでもALでの確認が安心。
- 運用のコツ:AL(6か月ごと)+SE(3〜6か月ごと)の二軸管理。同じ機器・同じ時間帯で測る/左右差も併せて記録。
ご注意:ここで示す数値や基準は一般的な目安です。症状や測定条件によって解釈は変わります。自己判断は避け、必ず主治医と相談して評価・治療方針を決めてください。
進行が始まってしまったら(必要に応じて)
- 低濃度アトロピン点眼/DIMS等の近視抑制眼鏡/近視抑制1dayコンタクト/オルソKを年齢・生活に合わせて選択(視力を守る4つの習慣も継続する)
- 評価のポイント:裸眼視力だけでなく、眼軸長の伸びが遅くなっているか
例えるなら、歯みがき(家庭)+定期検診(眼科)+必要な治療(医療)の三位一体。今の快適さと将来の目の健康を、両方守ります。
『ホームワック』の役割—調節の“こり”をほぐすスイッチ。賢い活用法
 ホームワックとは?
ホームワックとは?遠近の視覚刺激で毛様体(ピント合わせ)のこりをほぐし調節力を高める、家庭用の視力トレーニング。いわば“家庭でできるワック”。日内の見え方の揺らぎや疲れ目の軽減、生活ルールの習慣化の“スイッチ”づくりに役立ちます。使うときは、窓の外の遠景や部屋のいちばん遠い目標に視線を置き、「遠方視×トレーニング」を同時に行うのがコツです。
向いているお子さま
- A/B判定で、夕方に見えづらい/休憩で楽になるなど調節不安定のサインがある
- 通院のワック通いが続きにくい家庭(共働き・距離の問題など)
- C/D判定のケースでは、近視の食い止めを目指しての取り組み
使い方(失敗しない導入手順)
- まず眼科で“現状把握”:正確な度数検査(目薬でピント調節を一時オフにして測る)+眼軸長で現状を把握
- 視力を守る4つの習慣に取り組む(屋外・距離・休憩・睡眠)
- 「視力向上可能性判定」の活用&導入相談:お子さまのタイプ(調節のこり/生活習慣/学習環境)を整理し、取り組みの優先順位を決める。→ 迷ったら私たち眼育総研にご相談ください
- ホームワック 20分/日×3〜6か月トライアル:生活の同じ時間帯に固定して“習慣化”
- 中間評価(3か月):見え方の安定と生活改善の定着をチェック
- 再評価(6か月):眼軸長と度数の推移で進行の有無を確認し、ホームワックの目標(頻度・時間帯・継続期間)を再設定(※治療中でも継続可)
ホームワックの役割は?
- ホームワックは眼軸の伸びを直接止める治療ではありません。近視進行の本丸は生活改善+必要に応じた近視抑制治療。ホームワックは目のコリをほぐし調節力をアップ、家庭での施策を続けやすくする補助です。
- 「-0.5D前後なのに黒板が見えにくい」など度数の割に見えにくいケースでは、調節緊張・ストレス要因が疑われ、生活改善とホームワックのトレーニングにより、裸眼視力向上の可能性があります。
今日からのアクション
- 可能性を診断してみる(数分で視力向上の可能性をチェック)
- 学校の視力検査A判定でも不安? Web視力検査はこちら で今の見え方を確認(※自覚検査は目安。受診の代わりではありません)
- 机まわりを“30cm設計”に:タブレットスタンド、適切な椅子、デスクライト
- 家族で“2時間屋外”の予定を先に入れる(分割OK)
よくある質問(FAQ)
 Q1. 学校の視力検査A判定でも眼科受診は必要?
Q1. 学校の視力検査A判定でも眼科受診は必要?A. 不安があれば受診を。正確な度数検査+眼軸長でベースラインを作ると、今後の判断がしやすくなります。
A.調節緊張(仮性近視)のサインかもしれません。距離・休憩・姿勢を整え、必要に応じてホームワックで調節のこりケアを。
A. 30cmの距離・5分〜30分ごとの休憩・屋外2時間・十分な睡眠の4つが基本です。
A. 画面は目線より少し下、10〜20°前傾、明るさの確保、椅子と机で姿勢(ひざ90°・ひじ水平)を整えましょう。
用語解説
-
- 正確な度数検査(目薬でピント調節を一時オフにして測る):いわゆる「調節麻痺下屈折」。子どもはピントを強く合わせてしまいがちで、通常の度数検査(オートレフ)だと近視寄りに出やすい(過矯正になりやすい)ことがあります。目薬で一時的に調節を止めて“本当の度数”を測るのが小児では基本です。
- オートレフの度数(通常の屈折検査):器械で素早く測る度数。日々の変動や調節の影響を受けやすく、子どもでは参考値として扱います(眼鏡処方や経過判断には上記の“正確な度数検査”を推奨)。
- 眼軸長(AL):目の奥行き(角膜から網膜までの長さ)。長くなるほど将来リスク(病的近視・網膜剥離・緑内障など)が上がるため、6か月ごとのモニタリングが役立ちます。
視力回復辞典(視力回復の真実)
おすすめタグ
人気記事ランキング

学校の視力検査A判定でも油断禁物—近視予防と『ホームワック』活用ガイド

自宅でできる視力回復トレーニング方法を徹底解説

スマホが原因で斜視に?増える”スマホ斜視”とその対策

眼科のワックは効果がないって本当?

ホームワックは効果なし?近視は本当に良くなるの?
関連記事

学校の視力検査A判定でも油断禁物—近視予防と『ホームワック』活用ガイド

自宅でできる視力回復トレーニング方法を徹底解説

スマホが原因で斜視に?増える”スマホ斜視”とその対策

眼科のワックは効果がないって本当?

ホームワックは効果なし?近視は本当に良くなるの?

学校検眼で「近視」と言われたら──できることから、始めてみませんか?

アムスラーチャートとは?見え方の変化でわかる目の異常

目の健康寿命を延ばす!アイフレイル予防の決定版ガイド