この記事では、自宅で簡単にできる視力回復トレーニングの方法や、トレーニングを行う上での注意点、さらに効果を高めるためのポイントを詳しく解説します。
視力回復トレーニングとは?

トレーニング方法は多岐にわたり、目の筋肉を鍛える運動や、ピント調節機能を改善するエクササイズ、生活習慣の見直しなどが含まれます。
これらのトレーニングは、目の疲れを軽減し、視力低下の進行を遅らせる効果が期待されています。
近年、スマートフォンやパソコンなどのデジタルデバイスの使用増加に伴い、目の疲れや視力低下に悩む人が増えています。
視力回復トレーニングは、このような現代社会における目の健康問題に対する有効な対策の一つとして注目されています。
ただし、視力回復トレーニングの効果には個人差があり、全ての人に効果があるとは限りません。
また、トレーニングだけで視力が大幅に改善するわけではなく、生活習慣の改善や適切な休息と組み合わせることが重要です。
視力回復トレーニングの基本的な考え方
視力回復トレーニングの基本的な考え方は、目の筋肉を鍛え、血行を促進し、ピント調節機能を改善することです。
私たちの目は、近くのものを見るときにピントを合わせるために、毛様体筋という筋肉を収縮させます。
長時間近くのものを見続けると、毛様体筋が緊張し、ピント調節機能が低下してしまいます。
視力回復トレーニングでは、遠くのものを見たり、眼球を動かしたりすることで、毛様体筋の緊張をほぐし、柔軟性を回復させます。
また、目の周りの筋肉をマッサージしたり、温めることで血行を促進し、目に必要な栄養を届けやすくします。
これらのトレーニングを継続することで、目の疲れを軽減し、視力低下の進行を遅らせることが期待できます。
ただし、トレーニングの効果には個人差があり、全ての人に効果があるとは限りません。
なお、トレーニングだけで視力が大幅に改善するわけではなく、生活習慣の改善や適切な休息と組み合わせることが重要です。
トレーニング前に知っておくべきこと
視力回復トレーニングを始める前に、いくつか知っておくべきことがあります。
まず、視力低下の原因を特定することが重要です。
視力低下の原因は、近視、遠視、乱視などの屈折異常、加齢によるピント調節機能の低下、目の病気など様々です。
現在の目の状態や生活習慣の見直しにより、トレーニングの効果が期待できます。
ただし、視力の低下にはさまざまな原因があるため、効果的なトレーニングを行うには、まず眼科医に相談し、原因を明確にすることをおすすめします。
また、トレーニングの効果には個人差があります。
すぐに大きな変化が見られなくても、焦らず、継続的に取り組むことが改善への近道です。
トレーニング中に痛みや違和感を感じた場合は、すぐに中止し、眼科医に相談してください。
特に目の病気がある方は、症状が悪化する可能性もあるため、慎重に進めましょう。
トレーニングは、明るすぎず暗すぎない適度な照明の下で行い、リラックスできる環境を整えることが大切です。
事前に手を清潔にしておくことも忘れずに行いましょう。
トレーニングを行う上での注意点
視力回復トレーニングを始めるにあたっては、いくつかの注意点を押さえておくことが大切です。
まず、無理に行うのは避けましょう。
目に痛みや違和感を感じた場合は、すぐに中止し、眼科医に相談してください。
過度なトレーニングは、かえって目の疲労や視力の悪化を招くことがあります。
トレーニングは毎日コツコツ継続することが効果につながりますが、すべてのプログラムを日替わりにする必要はありません。
いくつかのメニューをバランスよく組み合わせながら、一部は継続的に同じ内容を行うことで、特定の機能をじっくり鍛えることも効果的です。
また、トレーニング内容によっては、姿勢や環境が影響するものもあります。
とくに近くを見るトレーニングや体の動きを伴う場合には、猫背や前かがみの姿勢が目の負担となることもあるため、できるだけ正しい姿勢を意識しましょう。
効果を確認するためには、定期的な視力検査もおすすめです。
トレーニングの成果や目の状態を客観的に把握することで、必要に応じて内容を調整し、より効率よく進めることができます。
自宅で簡単にできる視力回復トレーニング

特別な道具や器具は必要なく、日常生活の中で手軽にできるものがほとんどです。
これらのトレーニングを習慣化することで、目の疲れを軽減し、視力低下の進行を遅らせる効果が期待できます。
ここでは、自宅で簡単にできる代表的な視力回復トレーニングをいくつかご紹介します。
遠近体操、眼球運動、温冷アイマスクなど、どれも手軽に始められるものばかりですので、ぜひ試してみてください。
これらのトレーニングは、あくまで補助的なものであり、視力を大幅に改善するものではありません。
しかし、目の健康を維持し、視力低下を防ぐためには有効な手段となります。
トレーニングを行う際は、無理のない範囲で、毎日継続して行うことが大切です。
トレーニング中に目に痛みや違和感を感じた場合は、すぐに中止して、眼科医に相談してください。
遠近体操で目のピント調節機能を鍛える
遠近体操は、目のピント調節機能を鍛えるための代表的なトレーニング方法です。
近くのものと遠くのものを交互に見ることで、毛様体筋を伸縮させ、ピント調節機能を改善します。
具体的なやり方は、まず、人差し指を目の前に約30cm離して立てます。
次に、人差し指を数秒間見つめ、その後、遠くの景色(5m以上先)を数秒間見つめます。
この動作を10回程度繰り返します。
ポイントは、近くのものを見るときはしっかりとピントを合わせ、遠くのものを見るときはリラックスして見ることです。
遠近体操は、場所を選ばずにどこでもできるため、仕事の休憩時間や移動中など、ちょっとした隙間時間に行うことができます。
毎日継続して行うことで、目の疲れを軽減し、ピント調節機能を改善する効果が期待できます。
トレーニングを行う際は、無理のない範囲で、毎日継続して行うことが大切です。
また、トレーニング中に目に痛みや違和感を感じた場合は、すぐに中止して、眼科医に相談してください。
眼球運動で目の周りの筋肉をほぐす
眼球ストレッチは、目の周りの筋肉をほぐし、血行を促進する効果が期待できるトレーニングです。
このストレッチは、目の疲労を軽減し、視力低下の予防につながる可能性があります。
具体的な方法としては、まず、目を大きく見開き、次に、目を強く閉じます。この動作を数回繰り返します。
次に、正面を向いたまま、目を閉じてリラックスします。
目をゆっくりと開いたら、顔は動かさず、眼球だけを右に向けて数秒間静止します。
同様に、左、上、下、斜め右下、斜め左上、斜め右上、斜め左下の順に、眼球だけをゆっくりと動かし、それぞれ数秒間キープします。
眼球ストレッチを行う際には、首や肩の力を抜き、リラックスした状態で行うことが重要です。
また、痛みや不快感を感じた場合は、すぐに中止してください。
眼球の動きを意識して丁寧に行うことで、目の周りの筋肉を柔らかくし、血行を促進し、目の健康をサポートします。
温冷アイマスクで血行促進
温冷アイマスクは、目の周りの血行を促進し、筋肉の緊張をほぐす効果が期待できるアイテムです。
温めることで血管が拡張し、血流が良くなり、目に栄養が届きやすくなります。
また、冷やすことで炎症を抑え、目の充血や腫れを軽減する効果があります。
温冷アイマスクの使い方は簡単で、電子レンジや冷蔵庫で温めたり冷やしたりして、目の上に乗せるだけです。使用時間は、10分から15分程度が目安です。
温冷アイマスクは、目の疲れを感じたときや、長時間パソコン作業を行った後などに行うと効果的です。
寝る前に使用することで、リラックス効果を高め、睡眠の質を向上させる効果も期待できます。
市販の温冷アイマスクには、様々な種類があります。
ジェルタイプのアイマスクや、天然素材を使用したアイマスクなど、自分の好みに合わせて選ぶことができます。
温冷アイマスクを使用する際は、温度に注意してください。
熱すぎたり冷たすぎたりすると、目に負担をかける可能性があります。
毎日継続して使用することで、目の周りの血行を促進し、筋肉の緊張をほぐし、目の疲れを軽減する効果が期待できます。
生活習慣を見直して視力低下を防ぐ

長時間のデジタルデバイスの使用を控えたり、適切な明るさの環境で作業したり、バランスの取れた食事を摂ったりするなど、様々な対策があります。
ここでは、視力低下を防ぐために見直すべき生活習慣について、詳しく解説します。
正しい姿勢を保つこと、十分な睡眠をとること、ブルーライト対策を行うことなど、どれも日常生活で簡単に実践できるものばかりですので、ぜひ参考にしてみてください。
これらの生活習慣の改善は、視力低下を防ぐだけでなく、全身の健康維持にもつながります。
健康的な生活習慣を心がけることで、目の健康も守りましょう。
正しい姿勢を保つ

視力低下を防ぐためには、日々の姿勢を見直すことがとても重要です。
特に猫背や前かがみの姿勢は、目に余分な負担をかけてしまい、結果的に視力の悪化を招く原因になることもあります。
正しい姿勢とは、背筋がまっすぐに伸び、肩の力が抜けてリラックスしている状態です。
椅子に座るときは、深く腰をかけ、背中をしっかりと背もたれに預けることが基本。
足裏全体が床につくように、高さも調整しましょう。
しかし、長時間のデスクワークでは、つい前傾姿勢になってしまいがち。
そんなときに役立つのが「グラッチェア®」です。
体幹を自然に意識させるバランス設計で、座るだけで正しい姿勢をサポート。
無理なく背筋が伸びるので、目への負担も軽減され、視力低下対策としても効果的です。
また、パソコン作業では、画面と目の距離を40cm以上あけ、画面が目の高さにくるよう調整するのもポイント。
下を向き続ける姿勢は、首や肩に負担をかけ、結果として目の疲れにつながります。
同じ姿勢を続けること自体が体にとっては負担ですので、30分に一度は軽く立ち上がり、ストレッチを取り入れる習慣もおすすめです。
「姿勢が変わると、目もラクになる」
グラッチェア®を日常に取り入れて、体にも目にもやさしい習慣を始めてみませんか?
十分な睡眠をとる

目の健康を保つうえで、十分な睡眠は欠かせません。
睡眠不足が続くと、目の筋肉が休まらず、疲れがたまりやすくなります。
さらに、ドライアイやピント調節機能の低下にもつながり、視力への悪影響を招くことも。
睡眠中は、目の筋肉がしっかりと休息・修復される大切な時間です。
そのためにも、毎日7~8時間程度の質の高い睡眠をとることが理想とされています。
決まった時間に寝起きすることで、体内時計が整い、自然な眠りに入りやすくなります。
ただし、寝る前にスマートフォンやパソコンなどの強い光を浴びると、脳が昼間と勘違いし、眠りの質が低下してしまいます。
そこでおすすめなのが、赤い光で自然な眠りを促す『ユメミライト』です。
ユメミライトは、眠りに適した赤色波長のやさしい光を採用。
NASAの研究にも基づき、脳と体をスムーズにおやすみモードへと導いてくれます。
寝る1時間前に点灯するだけで、リラックスした気分に包まれ、デジタルデトックスにも最適です。
「眠る前の時間」を整えることで、翌朝の目のスッキリ感が変わります。
毎日の視力ケアは、夜の過ごし方から。
ユメミライトと一緒に、目と心を休める新習慣を始めてみませんか?
ブルーライト対策を行う

ブルーライトは、スマートフォンやパソコンなどのデジタルデバイスから発せられる光の一種です。
ブルーライトは、エネルギーが強く、目に負担をかけ、視力低下を招く可能性があります。
ブルーライト対策としては、ブルーライトカットメガネを使用したり、デジタルデバイスの画面設定でブルーライトを軽減するモードにしたりすることが挙げられます。
また、ブルーライトカットフィルムを画面に貼ることも有効です。
ブルーライトは、睡眠の質を低下させる可能性もあります。
寝る前にデジタルデバイスを使用する際は、ブルーライトカット機能を使用したり、使用時間を短くしたりするなど、工夫しましょう。
ブルーライト対策を行うことで、目の負担を軽減し、視力低下を防ぐことができます。
デジタルデバイスを長時間使用する際は、積極的にブルーライト対策を行いましょう。
視力回復のために検討できるその他の方法
ここでは、視力回復のために検討できるその他の方法として、低濃度アトロピン、オルソケラトロジー、レーシック、視力回復トレーニングなどをご紹介します。
これらの方法は、専門的な知識や技術が必要となるため、眼科医に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
これらの方法は、全ての人に効果があるわけではありません。
副作用やリスクも伴う場合がありますので、十分に理解した上で、慎重に検討しましょう。
低濃度アトロピン

低濃度アトロピンは、小児の近視進行を抑制する目的で使用される点眼薬です。
もともとは散瞳薬として用いられていたアトロピンですが、ごく低い濃度で使用することで副作用を抑えつつ、近視の進行を遅らせる効果が報告されています。
ただし、低濃度アトロピンは近視の原因そのものを取り除く治療法ではありません。
あくまで進行を「遅らせる」ための選択肢のひとつであり、効果には個人差があるほか、根本的な改善には至らないケースも多くあります。
副作用としては、瞳孔が開いた状態が続くことによるまぶしさやピント調節の困難が報告されています。
そのため、使用にあたっては眼科医の指導のもと、適切な用法・用量を守ることが重要です。
また、定期的な受診で目の状態や視力の変化を確認してもらう必要があります。
低濃度アトロピンは、進行抑制の「補助的な手段」としては有効ですが、それだけに頼るのではなく、目に負担のかかる生活習慣を見直すことや、適切な視力矯正、日常の姿勢や光環境の改善など、トータルでの対策が欠かせません。
「薬に頼りきる」のではなく、「環境と習慣を整えながら活用する」──
そうしたバランスの取れた視力ケアが、将来の目の健康を守る鍵となります。
オルソケラトロジー

オルソケラトロジーは、夜間に特殊なハードコンタクトレンズを装用し、睡眠中に角膜の形状を物理的に矯正することで、日中の裸眼視力を一時的に改善する方法です。
近年では、近視進行の抑制効果も期待されており、特に小児への使用が広がっています。
しかしながら、オルソケラトロジーは視力低下の根本的な原因を解決する治療ではありません。
あくまで「裸眼で過ごせる時間を作る」ことや「進行を抑える」ことを目的とした対処法のひとつです。
また、角膜の状態や近視の程度によっては適応とならない場合もあります。
装用には、感染症のリスクや角膜への負担といった注意点も伴うため、事前に眼科医の十分な診断を受けたうえで、安全に管理する必要があります。
レンズの取り扱いには清潔さと正しい手順が欠かせません。
眼科医の指導のもと、装用方法やケアを正確に守り、定期的な受診で目の状態をしっかり確認してもらいましょう。
オルソケラトロジーを検討する際は、生活習慣の見直しや目にやさしい環境づくりといった日常的な対策もあわせて行うことが大切です。
一時的な視力改善にとどまらず、将来の目の健康を見据えた包括的なケアを心がけましょう。
ICL(眼内コンタクトレンズ)
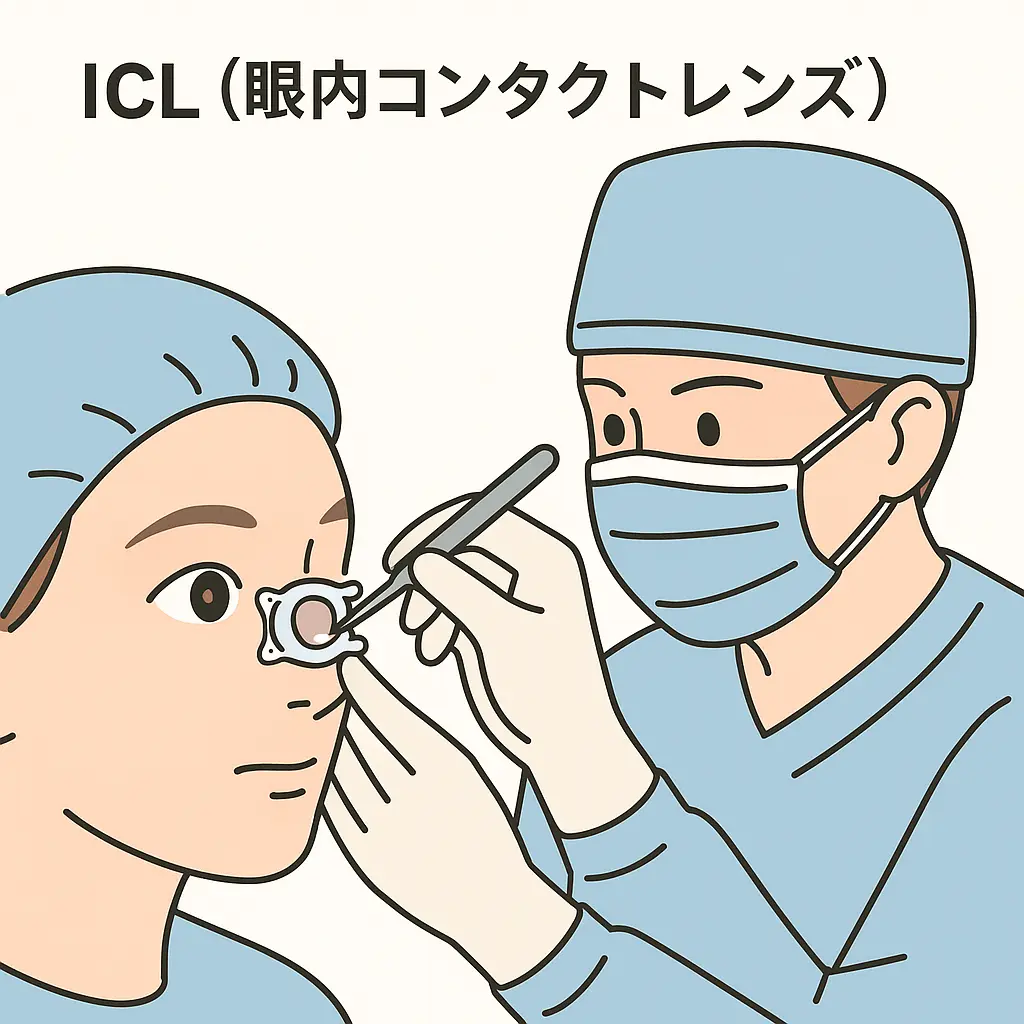
ICL(眼内コンタクトレンズ)は、目の中に小さなレンズを挿入し、屈折異常を矯正する手術です。
角膜を削るレーシックとは異なり、角膜を温存できるため、手術後のドライアイリスクが比較的低いというメリットがあります。
近視・遠視・乱視など幅広い屈折異常に対応でき、レーシックの適応外とされる強度近視の方にも選択肢となる場合があります。
ただし、ICLは視力の低下を防ぐための予防策ではなく、あくまで視力を矯正するための外科的手段です。
生活習慣や環境によって再び視力が低下する可能性もあるため、根本的な解決策とは言えません。
さらに、手術には専門的な技術と経験が必要であり、事前に適応検査を受けたうえで、信頼できる眼科医のもとで慎重に進める必要があります。
手術後も定期的な検診を欠かさず、感染症やレンズのずれといった合併症のリスクにも注意が必要です。
また、ICLは自由診療となるため、費用が高額(数十万円程度)になる点も考慮しておく必要があります。
ICLは、視力矯正の「手段」としては有力ですが、それだけに頼るのではなく、目の健康を守るためには日常生活の改善や定期的なケアも欠かせません。
「見える」を長く保つためには、医療と生活の両面からのアプローチが重要です。
レーシック

レーシックは、角膜にレーザーを照射してその屈折率を変え、近視・遠視・乱視などの屈折異常を矯正する視力回復手術の一つです。
手術自体は短時間で済み、術後すぐに視力回復を実感できるケースも多いため、多くの人が選択肢として検討しています。
ただし、レーシックは視力低下の根本原因(生活環境や目の使い方)を解決するものではありません。
術後の生活習慣によっては、再び視力が低下する可能性もあることを理解しておく必要があります。
また、角膜の厚みや形状によっては、レーシックが適応外となる場合もあります。
手術を検討する際は、事前に精密な検査を受け、自身が適応かどうかを判断してもらいましょう。
手術後には、ドライアイ、夜間のまぶしさ(ハローやグレア)といった副作用が起こることがあり、人によっては長期的に不快感を感じる場合もあります。
レーシックは自由診療であり、数十万円単位の費用がかかる点や、不可逆的な手術であることも含め、慎重に判断することが大切です。
視力矯正の一つの選択肢としてレーシックを考える際には、日々の目の使い方や生活習慣の見直しと併せて行うことで、より長く健康な視力を保つことができます。
眼科でワック

眼科で行われる「ワック」と呼ばれる治療は、正式には「調節機能解析装置」や「立体視機能回復装置」などを用いて、目のピント調節機能を一時的に改善するための治療です。
目の筋肉を刺激し、血流を促進することで、ピントを合わせる力の回復を目指します。
この治療は、主に仮性近視やVDT症候群(テクノストレス眼症候群)など、ピント調節機能の低下が原因で起こる視力低下に対して効果があるとされています。
ただし、ワック治療はすべての視力低下に対して万能な治療法ではありません。
目の筋肉の機能が一時的に改善しても、根本的な原因である生活習慣(長時間の近距離作業・姿勢・睡眠不足など)が変わらなければ、視力の回復は持続しにくいのが実情です。
治療は、眼科医の判断に基づいて行われ、期間や頻度は症状によって異なります。
副作用は少ないとされていますが、一時的に目の疲れやかすみを感じることもあります。
大切なのは、ワック治療を一つの手段として活用しながら、生活環境や目の使い方を見直すことです。
目に負担の少ない姿勢・照明・作業時間の管理などを整えることで、治療の効果もより長続きしやすくなります。
「治療に通うだけ」ではなく、「日常で整える」視力ケアもあわせて取り入れることが、目の健康を守るうえでの鍵となります。
ソニマックやミオピアなどの超音波

ソニマックに代表される超音波機器。
超音波の微細な振動で目の周囲の筋肉を刺激し、血行を促進することによって、眼精疲労や仮性近視の改善を目指す医療機器です。
仕組みとしては、肩こりのケアに使われる超音波治療器と類似しており、筋肉の緊張を一時的に和らげることで、症状を軽減させます。
しかし、肩こりがマッサージや温熱療法で一時的に良くなっても、同じ姿勢や生活が続けばすぐに再発するように、
ソニマックによる目の疲労改善も、根本的な原因(長時間の近距離作業、姿勢の悪さ、睡眠不足など)が改善されなければ再び繰り返される可能性があります。
つまり、ソニマックは一時的にほぐすためのサポート機器であって、視力を持続的に回復させる治療法ではありません。
使用にあたっては、眼科医の指導のもと、適切な方法と頻度で行うことが前提です。
また、目に違和感や異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、受診してください。
副作用は少ないとされていますが、妊娠中の方や目に持病のある方は使用を控えるべきとされています。
大切なのは、こうした機器に頼るだけでなく、目を酷使しない生活環境の整備や、適切な姿勢・照明・作業時間の管理など、日常的な目のセルフケアと併せて活用することです。
「ほぐしても、また凝る」ように、「楽になっても、また疲れる」──
目のケアも、根本から見直すことが持続的な改善への近道です。
ホームワック

ホームワック®は、眼科で行われる「ワック治療」を自宅で手軽に再現できるよう開発された、家庭用視力トレーニング機器の決定版です。
病院に通わなくても、自宅で“見る力”を鍛えることができる唯一の視力トレーニング機器として注目されています。
一般的な視力ケアが「一時的に疲れをとる」「リラックスさせる」ものであるのに対し、ホームワック®は目のピント調節機能を“鍛える”ことを目的としたアクティブなトレーニング機器です。
ホームワック®の特長は、単に遠くと近くを交互に見る「遠近トレーニング」だけではありません。
現代人に多い近視傾向(特に近くを見るときに目が寄りすぎる寄り目傾向)を改善するために、目の筋肉のバランスを整える「開散(目を外に開く力)」と「輻輳(目を内に寄せる力)」の調整トレーニングにもアプローチできる設計になっています。
そのため、ホームワック®は「見る力の土台」を整えることができ、特に以下のような方におすすめです。
- 仮性近視と診断されたお子さま
- 長時間スマホやゲームで近くを見ることが多い方
- 眼精疲労やピントのぼやけが気になる方
- 眼科に継続して通うのが難しいご家庭
使い方は簡単で、テレビやYouTubeを1日20分程度ホームワック®で見るだけ。
自然な動作の中で、目が本来持っている調節機能を無理なく引き出します。
通院の必要がなく、自宅で毎日コツコツ継続できるのも、大きなメリットです。
まとめ – 自宅でできる視力回復トレーニング方法を徹底解説
自宅で気軽に取り組める方法から、医療機関で行う専門的な治療まで、目的や状況に応じた多様な選択肢があります。
トレーニングを始める際には、まず自分(あるいはお子さま)の視力低下の原因を正しく理解し、それに適した方法を選ぶことが大切です。
また、トレーニングの効果には個人差があるため、短期間での劇的な改善を求めるのではなく、生活習慣と組み合わせてコツコツ取り組むことで、より効果が期待できます。
特にお子さまの場合は、視力の状態が将来に大きく関わることもあります。
たとえば、将来的にレーシックを選択肢に入れるにしても、強度近視まで進行してしまうと手術の適応外となる可能性があります。
また、視力基準がある職業(パイロット・自衛官・警察官・スポーツ選手など)を目指す際、近視が進んでいるとその道が閉ざされることもあります。
たとえ1.0の視力に完全に戻らなかったとしても、「進行を食い止める努力」には、将来の選択肢を守る価値が十分にあります。
正しい姿勢、十分な睡眠、ブルーライト対策など、目にやさしい生活環境を整えることも、トレーニングと同じくらい大切です。
眼科での定期的なチェックも活用しながら、「見る力」を育てる生活を今日から始めてみませんか?
著者・監修者・運営情報
執筆
眼育総研事務局は、目の健康と視力ケアの情報サイト「視力ランド」を運営する編集部です。担当:太田(編集)
監修
監修範囲:医学的記述(一般的な症状説明・受診目安・注意喚起)
監修日:
運営
有限会社ドリームチーム
所在地:神奈川県横浜市青葉区田奈町43-3-2F / 連絡先:045-988-5123(視力ランド窓口):045-988-5124
表現設計について(薬機法・景表法・医療広告に配慮)
- 効能効果の断定(「治る」「改善する」等)は避け、一般的な情報と生活上の工夫に整理しています。
- 数値・作用機序に触れる場合は、一次情報(論文・公的機関資料)を参照し、出典を明記します。
- 症状が続く/強い場合は医療機関の受診をご案内します。
参考文献:本文末の「参考文献」セクションをご確認ください。
利益相反(COI):当記事には当社取扱商品の紹介が含まれる場合があります。
視力回復辞典(視力回復の真実)
おすすめタグ
人気記事ランキング

眼精疲労と肩こりがつらい…その不調、目の使い方が影響しているかもしれません

ドライアイ対策|つらい目の乾きをやわらげるセルフケアと予防習慣

眼精疲労の対策|つらい疲れ目を“ケア+予防”で楽にする対策

スマホが見えにくい…老眼の対策は“早めの対処”から|軽減のコツと環境づくり

子供の近視にショックを受けた親御さんへ|不安な気持ちと向き合う視力ケアの考え方
関連記事

眼精疲労と肩こりがつらい…その不調、目の使い方が影響しているかもしれません

ドライアイ対策|つらい目の乾きをやわらげるセルフケアと予防習慣

眼精疲労の対策|つらい疲れ目を“ケア+予防”で楽にする対策

スマホが見えにくい…老眼の対策は“早めの対処”から|軽減のコツと環境づくり

子供の近視にショックを受けた親御さんへ|不安な気持ちと向き合う視力ケアの考え方

子どもの近視が将来の眼病につながる?──家庭でできるリスクを減らす対策

目は一生の資産——3分で整えるピント調節 “ピントフレッシュ”のすすめ

学校の視力検査A判定でも油断禁物—近視予防と『ホームワック』活用ガイド





