
A判定ならさすがに安心か???
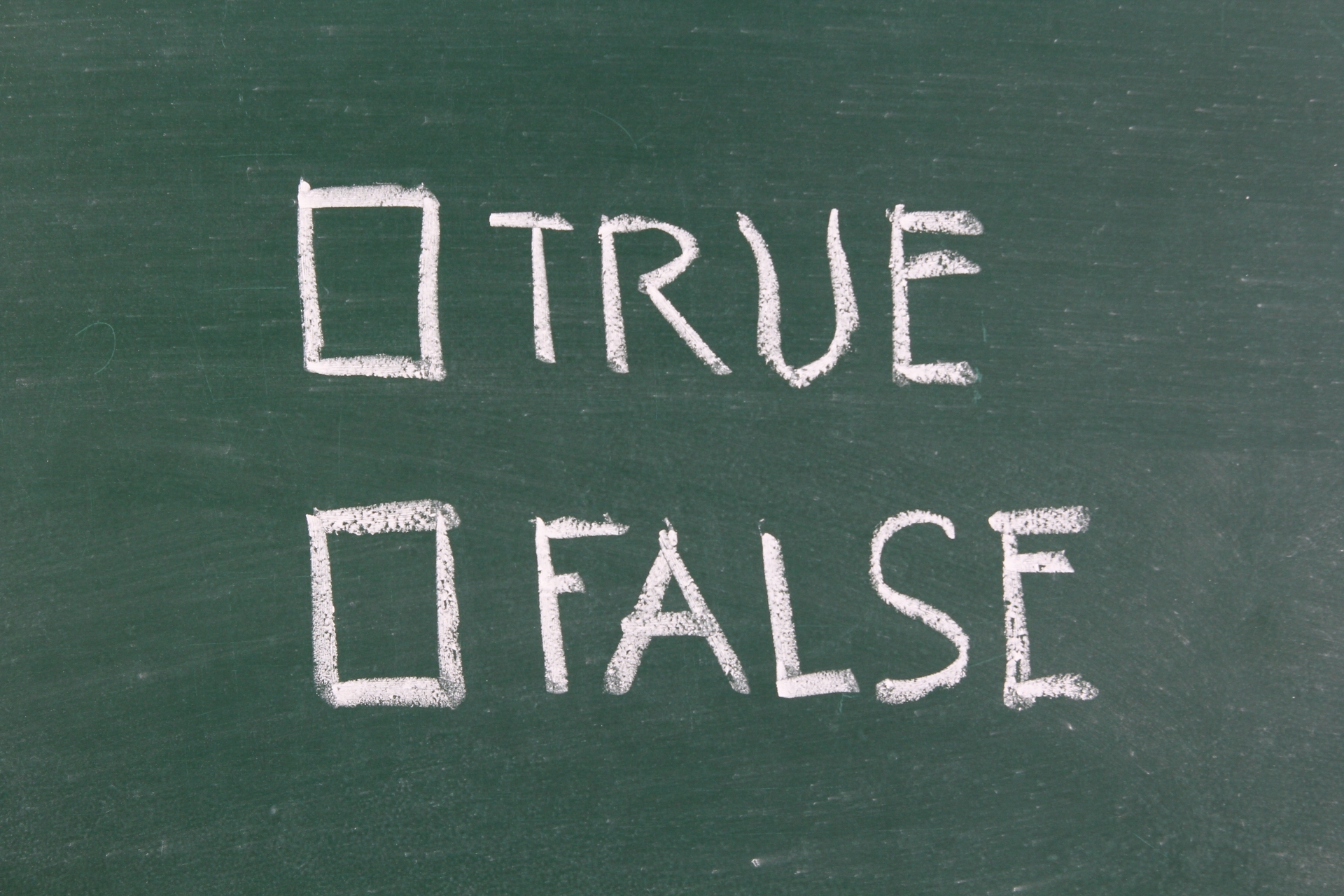
「最も危険なB判定!」というお話を、第7回でさせていただきました。
今回は、じゃあ、A判定なら本当に安心できる???
学校検眼だけにまかせておいていいの?
ということについて、考えていきます。
学校検眼の結果がA~Dで評価され、
判定 視力
A → 1.0以上
B → 0.7~0.9
C → 0.3~0.6
D → 0.2以下
という内容になっていることは、第7回で触れました。
また、“B評価は赤信号!”ということもお話しいたしました。
詳しくは、最も危険なB判定!でおさらいしてみて下さい。
さて、「B判定はアウト!」ということをおさらいしたところで、
じゃあ、さすがにA判定なら安心ですよね?ということなのですが…
視力低下を見落とすワナが…
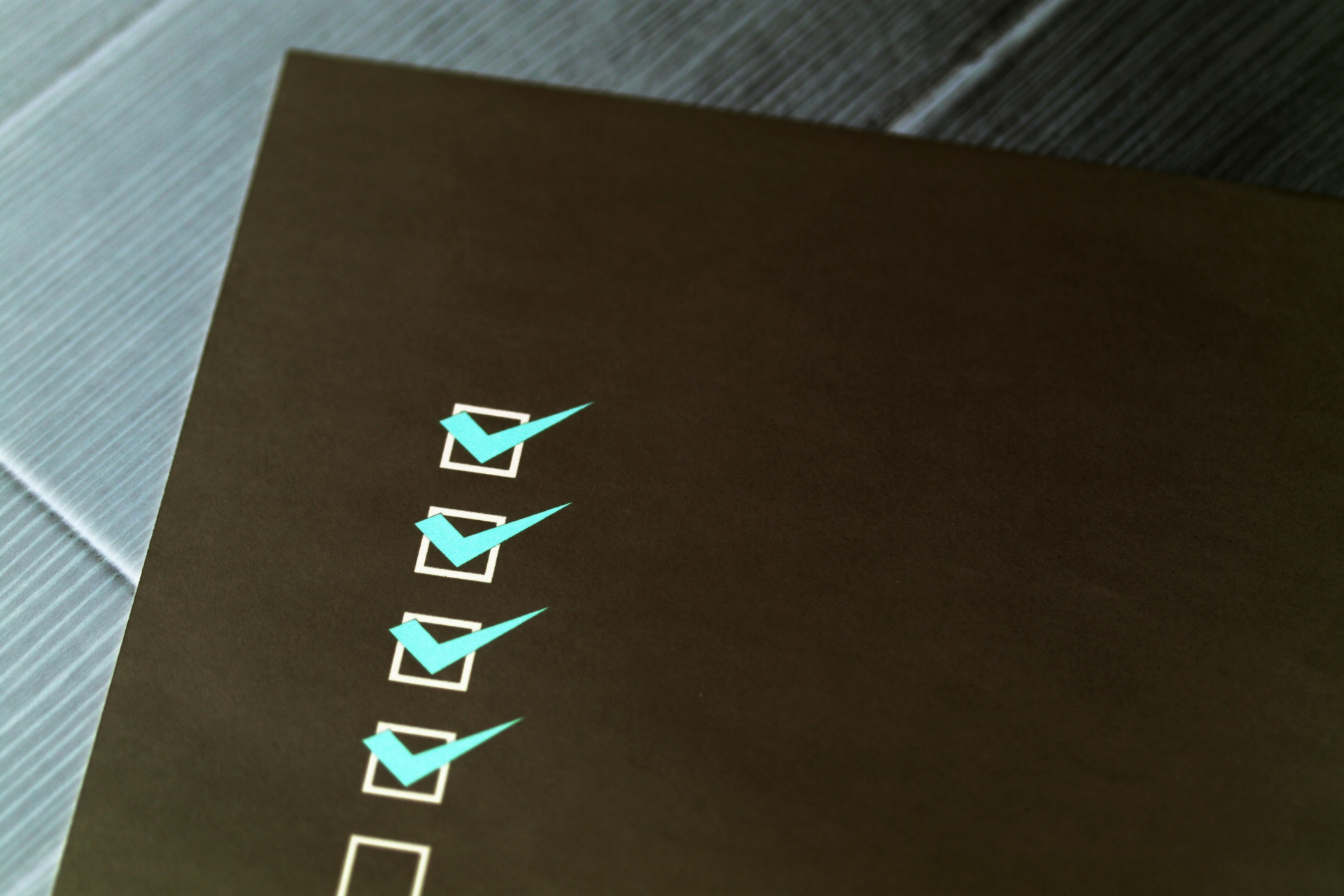
答えは、残念ながら「NO」!
A判定でも、中身はいろいろなのです。
A → 1.0以上
ということは、1.0でも1.5でもすべてA判定である、ということ。
地域によっては、1.2以上は測定しないところもあります。
去年1.5だった視力が、今年は1.0になっていたとします。
それでも、出てくる判定は、両方とも「A」。
1.5→1.0という視力低下の始まりが、これでは見落とされてしまいます。
見落とされたままでは、徐々に低下していくばかりですから、
「A判定だわ、よかった (実際の視力1.5)」
「今年もA判定ね、よかった (実際の視力1.0)」
…放置…
翌年
「えっ、いきなりC判定? ずっとAだったのに!」
「A」「B」「C」という判定だけを見ていると、「C」が出た時点で、突然視力が落ちたかのように感じられます。
実際はジワジワと進行していたわけですが、気づかれずに突然近視を突きつけられてしまう…
結構怖いものがあります。
もう1つ、学校検眼では、保健室などに検眼表を設置して、立ち位置を決めて、というふうに実施することが多いようです。
また、大勢の子どもが1度に検査を受けることを考えると、
1人1人にあまり時間をとってはいられない
自分の順番が来る前に、検眼表を覚えてしまう
など、きめ細かいやり方ができにくく、したがって、結果が正確でないことも…
実際より悪い判定が出たり、逆に良い判定が出たりすることも、考えられるわけです。
グレーゾーンに注意!

つまり、
A判定にも、
“本当に問題なし”である場合
“近視になり始めている”場合
がある、ということ。
2の場合、AはAでも既に”グレーゾーン”に入っているわけです。
大切なのは、ここで近視の兆候を認識できるかどうかなのです。
「A判定でも近視の兆候が出ていることがあるのはわかったけれど…」
「じゃあ、それを知るためにはどうすれば??」
それに役立つデータがあります。
「視力」だけからはわからない、「近視の進行度」を数値で表したもの
「えっ、そんな便利な数値って、あるの?!」
そう思った方、もしかして、前号第20回を読み過ごしたのでは??
いえいえ、大丈夫。今からでも十分間に合います。
「視力」より大事な『屈折度数!?』って何?をお読み下さい。
「屈折度数」のデータを得ることで、”問題なし”のA判定なのか、”グレーゾーン”に突入しているか…を知ることができるということをご理解いただければと思います。
近視は、”早期発見・早期対処”が最大のポイント。
視力がまだ高い間に、近視の兆候をつかむことができれば、それがいちばん効果的な近視予防といえます。
検眼シートをもらっちゃおう
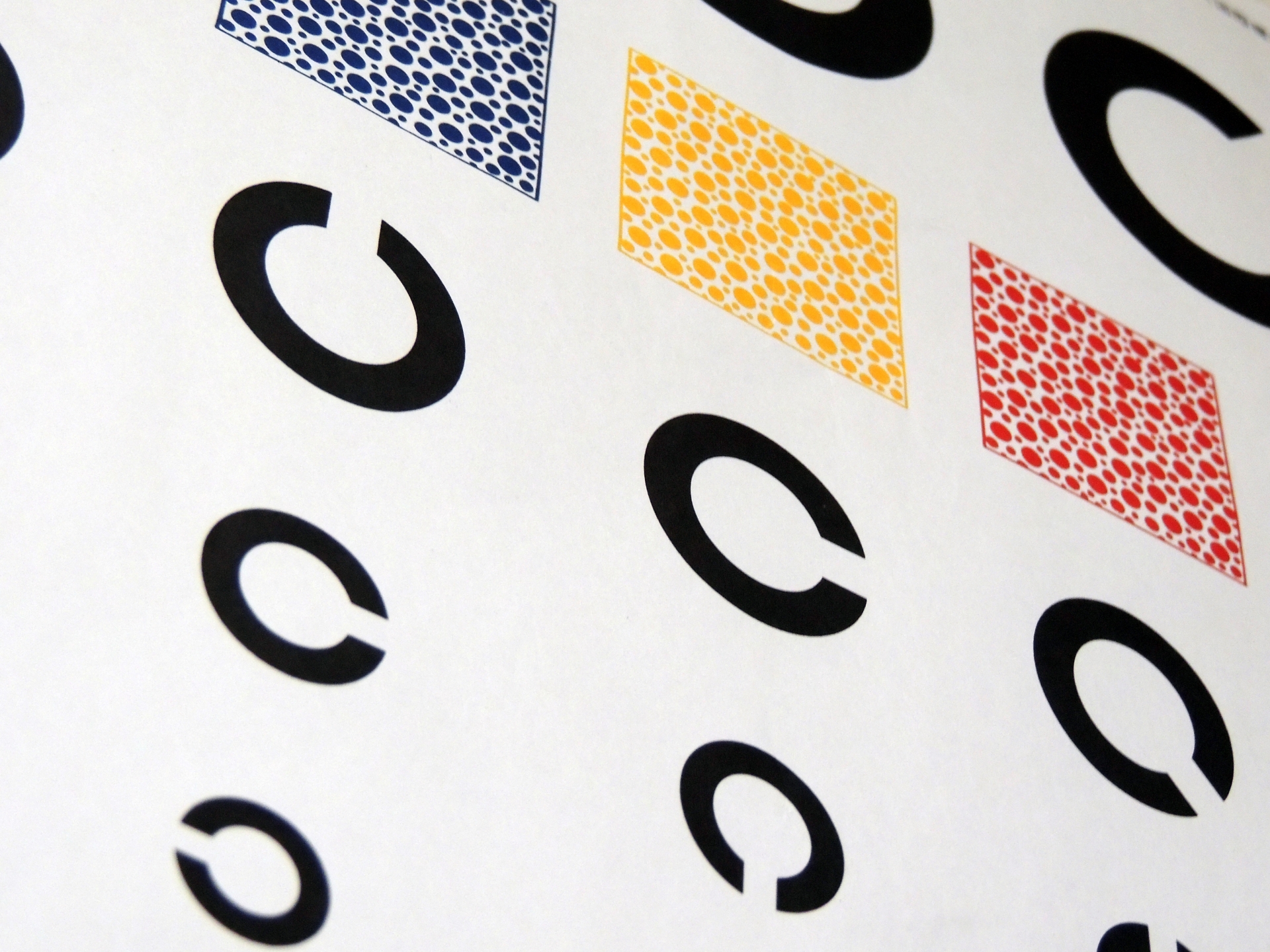
眼科、メガネ店などで、定期的に「屈折検査」をしてもらえば、それに越したことはありません。
小学校時代は視力低下のスピードが速いため、2~3ヶ月に1度のペースで、検診を受けるのが理想的です。
とはいうものの、悪くなっているかわからないのに、定期的に検査に通うのはなかなか難しいもの。
そこでおすすめなのが、『自宅で視力検査だけはしておく』という方法です。
そして、何らかの異常を発見した場合に、急いで屈折検査を受けに行きます。
といっても、どうやればいいの???
その際は、眼育(めいく)総研にお問い合わせください。
無料で家庭用検眼シートと、検眼方法をお送りします。
検眼シート付!視力トレーニング器機 ホームワックの資料請求(完全無料)♪
「近視スタートサイン」を見逃さない方法

「しかし、私が自宅で測定して、正確に測定できるのかしら…?」
と、ご心配の方もいらっしゃることでしょう。
それでは、自宅で検眼する際の、とっておきの方法をお教えします。
普段の生活の中で、近視のスタートサインを発見するのは、プロではない皆さんにとってはなかなか難しいことと思います。
ですが、検眼中には、目の使い方のクセがとってもでやすいのです。
見るポイントさえわかっていれば、「近視スタートサイン」を意外と簡単に発見して頂くことができます。
まずは、検眼の準備をしましょう。
1)検眼は立って行ってください。その方が、クセがでやすくなります。
自宅検眼では、しゃもじなどを使って片眼を隠しながら、右眼、左眼、両眼の順に検査してみてください。
月に1回程度のペースでやるのが、お勧めです。
2)検眼表は貼りっぱなしにせず、普段はしまっておきましょう。
向きを覚えにくくします。
◆近視スタートサインの発見法◆
検眼している際のお子さんの様子を、次のポイントに従って、観察してください。
☆目の使い方に異常がないか?☆
「細めていないか?」
「見開いていないか?」
「上目づかい・下目づかいになっていないか?」
「顔が正面から見て斜めになっていないか?」
☆リラックスしているか?☆
「肩に力が入っていないか?」
「呼吸はゆったりと行われているか?」
上記の項目に異常が見られず、あくまでもリラックスした状態で、左右それぞれで視力1.0以上、両眼の測定で1.2以上あれば、とりあえず安心して大丈夫。
ただし、左右それぞれの視力の数値が1.0以上でているとしても、
目の使い方にへんなクセがでていたり、身体に余計な力が入っているようだったら…
そんな場合は、それを「近視スタートサイン」と受け止めましょう。
「近視スタートサイン」とは、先ほどの”グレーゾーン”に入っている可能性を示すものです。
その場合は、屈折検査を受けてみることを、お勧めします。
屈折検査データの『6つの数値』(検査時に訊きましょう)と、裸眼視力の数値を、眼育(めいく)総研にメールや電話でお知らせ下さい。
6つの数値とは、左右それぞれの、屈折度数(球面レンズ・Sph)、乱視度数(円柱レンズ・Cyl)、矯正視力の値です。
その数値を元に、現在あなたの近視がどの程度進行しているのか、客観的に無料で詳しく解説いたします。→視力向上可能性判定
屈折検査のデータがあれば、ないときよりも、より詳しく精度の高い判定が受けられます。
まとめ
- 学校検眼の結果を過信しない
- 自宅で定期的に視力検査してみる
- その際、『近視スタートサイン発見法』を使う
近視を食い止めるには、「早期発見」がいちばんです!
早期発見のカギになるのが、自宅での検眼と、『近視スタートサイン発見法』です。
「早期発見/早期対処」の機会を逃さないために…
視力ランドでは、無料で視力向上可能性判定を実施しております。
フォームに必要事項を入力するだけで、その場で瞬時に可能性を判定します。
お気軽にご利用下さい!
著者・監修者・運営情報
執筆
眼育総研事務局は、目の健康と視力ケアの情報サイト「視力ランド」を運営する編集部です。担当:太田(編集)
監修
監修範囲:医学的記述(一般的な症状説明・受診目安・注意喚起)
監修日:
運営
有限会社ドリームチーム
所在地:神奈川県横浜市青葉区田奈町43-3-2F / 連絡先:045-988-5123(視力ランド窓口):045-988-5124
表現設計について(薬機法・景表法・医療広告に配慮)
- 効能効果の断定(「治る」「改善する」等)は避け、一般的な情報と生活上の工夫に整理しています。
- 数値・作用機序に触れる場合は、一次情報(論文・公的機関資料)を参照し、出典を明記します。
- 症状が続く/強い場合は医療機関の受診をご案内します。
参考文献:本文末の「参考文献」セクションをご確認ください。
利益相反(COI):当記事には当社取扱商品の紹介が含まれる場合があります。
視力回復辞典(視力回復の真実)
おすすめタグ
人気記事ランキング

スマホが見えにくい…老眼の対策は“早めの対処”から|軽減のコツと環境づくり

子供の近視にショックを受けた親御さんへ|不安な気持ちと向き合う視力ケアの考え方

子どもの近視が将来の眼病につながる?──家庭でできるリスクを減らす対策

目は一生の資産——3分で整えるピント調節 “ピントフレッシュ”のすすめ

学校の視力検査A判定でも油断禁物—近視予防と『ホームワック』活用ガイド
関連記事

スマホが見えにくい…老眼の対策は“早めの対処”から|軽減のコツと環境づくり

子供の近視にショックを受けた親御さんへ|不安な気持ちと向き合う視力ケアの考え方

子どもの近視が将来の眼病につながる?──家庭でできるリスクを減らす対策

目は一生の資産——3分で整えるピント調節 “ピントフレッシュ”のすすめ

学校の視力検査A判定でも油断禁物—近視予防と『ホームワック』活用ガイド

自宅でできる視力回復トレーニング方法を徹底解説

スマホが原因で斜視に?増える”スマホ斜視”とその対策

眼科のワックは効果がないって本当?





