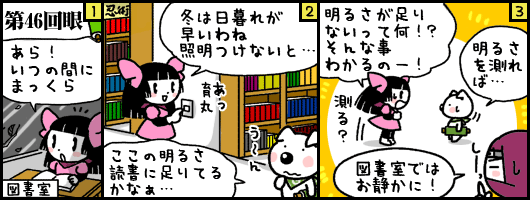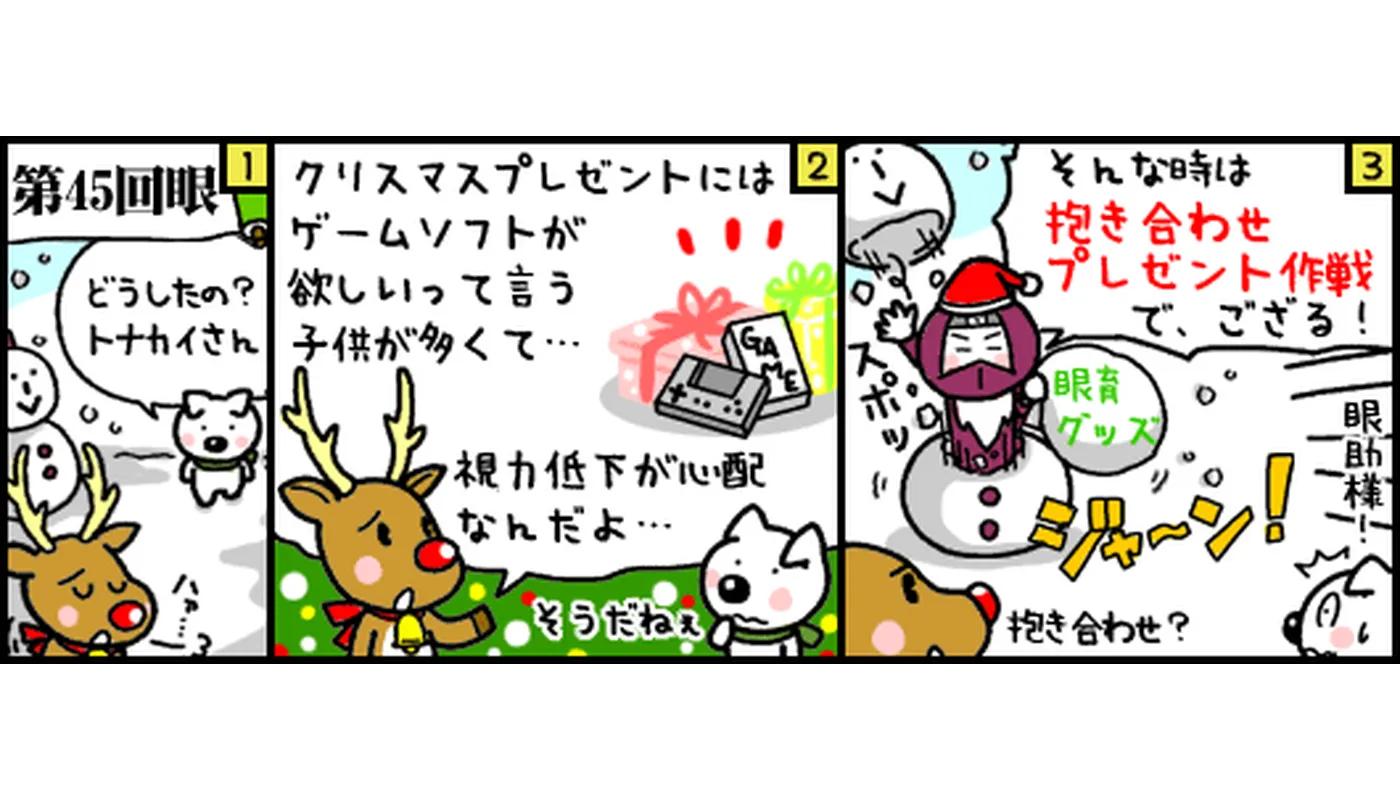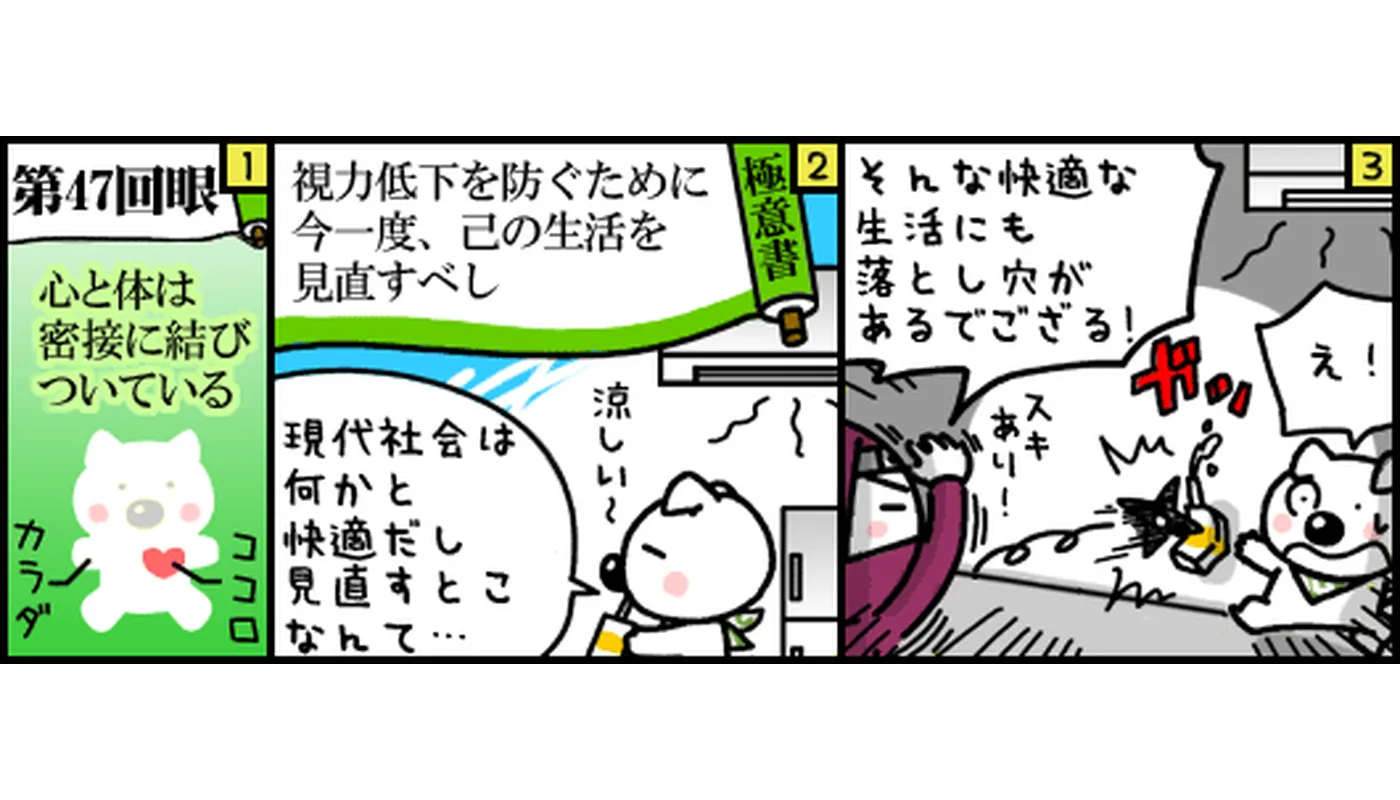はじめに

いよいよ年の瀬、先日は首都圏でも初霜が降り、冬もさらに深まりつつあります。
前回、ただでさえ寒くて外遊びが減り、家の中にいる時間が長くなるこの季節、クリスマスプレゼントのゲームソフトが輪をかけて子どもの近視が加速…
という話題をお送りしましたが――
ちょうど同じタイミングで、読売新聞の一面に気になる記事が載りました。
そのタイトルも、『園児の3割、視力「1.0未満」…外遊びしないから?』というもの。
「視力が1.0未満の幼稚園児が3割に迫ることが11日、文部科学省の学校保健統計調査でわかった。
視力の低下はテレビやゲーム機器、文部科学省は『外で遊ばず、家にいる時間が長いのが要因』と分析している。
調査は、今年4~6月に健康診断を受けた全国の幼稚園児と小中高校生から、約330万人のデータを抽出した。
それによると、視力が1.0未満の園児の割合は、前年度比2.7ポイント増の28.9%で、視力調査が始まった1979年度(16.5%)の2倍近くとなった。
子供の視力の低下傾向は続いており、小学生・中学生もともに過去最高。
今回の調査では、視力低下の低年齢化がさらに進行していることを裏付けている」(読売新聞記事より)
当メルマガでも、何度か近視の低年齢化については触れてきました。
年々、加速度的に進行する低年齢化は、とどまるところを知らない様相を呈している感があります。
今回は、そんな傾向を少しでも食い止めるのに必要な、あるポイントについて、考えてみたいと思います。
危ない!家の中で遊ぶ子どもの視力

幼稚園児の間で近視の傾向が高まっていることの原因として、『外で遊ばず、家にいる時間が長くなっている』というのは、十分にうなずける話です。
ゲームやビデオ・DVDなどの普及に加え、少子化や物騒な世の中…
などの要因が重なり、現代の子どもたちは昔に比べ、外遊びの割合がかなり少なくなっているのは確かでしょう。
さらに…
今、この季節は、そんな“家の中で遊ぶ子どもたち”の視力が、ひときわ危険にさらされやすいと言えます。
なぜなら…
1年でいちばん日の入りが早いと言われるのが、冬至の日(12月22日頃)。
ここを境にだんだん日が延び、ちょうど子どもたちの冬休みあたりが1年中でいちばん暗くなるのが早い
⇒1日のうちで暗い時間が長い期間にあたるわけです。
夕方4時を過ぎた頃にはすでに暗くなり始め、もうそんな時間??
と少々慌ててしまう…なんていうことが、この時期にはよくあるのではないでしょうか。
そんな時節柄、家の中で遊びに熱中している子どもたちも、気がついたら暗がりでゲームをしたりビデオを見たりしていた――などの状況が、とても生じやすいと言えます。
暗い所で距離の近い画面を見続ける、というのは、目にとってはまさに最悪の状態。
ただでさえ集中して凝視してしまいがちなのが子どもの特性ですが、暗い場所では、さらによく見ようと、目を凝らします。
それを続けるうちに…そう、近視が始まる危険性がいっぱい!なのです。
明るさって、測れるの??

ここで、「たしかにそうよね。じゃ、部屋の明かりは早めにつけるようにしましょう。」と言いつつ、照明のスイッチをパチッと点けたあなた。
ちょっと待ってください。
次にご紹介する体験談を、まずは読んでみていただきたいと思います。
『明るさ』と簡単にいうけれど、具体的にどうすればいいのか良くわかりませんでした。
今回、子供部屋の明るさがぜんぜん足りていないことにショックを感じました。
すぐ蛍光灯を取り替えて適切な明るさにしたら、今まで穴の中にいたんだな、と思えるくらいでした。
気分も明るくなったように思います。
今まで、僕がマンガを読んだり、プラモデルを作ったりしていた場所は、明るさが足りなくて目に悪い場所だったということが、よくわかりました。
夜、布団の中で小さいスタンドをつけて本を読んでいましたが、測ってみたら明るさが「0」だったので、びっくりしました。もう、やめようと思います。
勉強するときも、机の電気だけではなく、周りも明るくしてから始めるようにしました。
普段、十分に明るいと思っていた場所や環境が、実は“明るさ不足”だったとわかり、ショック!
という体験をされたお母さんやお子さんが、実際に寄せてくださったものです。
「明るさ」って、明かりをつければそれでOK、というものではないということを、身をもって体験されたわけですが、
でも、
- 子供部屋の明るさがぜんぜん足りていない
- 今までマンガを読んだりプラモデルを作ったりしていた場所は、明るさが足りなくて目に悪い場所だった
――これらのことは、一体どうやってわかったの?と、思われたのではないでしょうか。
それに、「測ってみたら明るさが『0』だったので、びっくりした」って、どういうこと?
明るさって、測れるの??とも思われたかもしれませんね。
「明るさ」って…実は、測れるんです!
測ってみました!結果は…

上の2つの体験談を書いてくださったのは、眼育明かりメータを使用された方々です。
眼育明かりメータとは…
目にとってとても重要な“適切な明かり”を使いこなすための、視力低下防止の強力アイテムです。※眼育明かりメータは販売終了いたしました。
あなたの周りの明るさ環境を、カンタン操作で一発計測。
勉強、読書、食事、団らん…
それぞれに最適な明るさが、一目瞭然!
今、私の手元に眼育明かりメータがあります。
手にとってみると…小さくて軽い、ということに、まずビックリ。
明かりメータというネーミングから、 専門的な”照度計”を想像する方もいるかもしれませんが、一般的なゴツい”照度計”とは全然違い、手のひらサイズで、これならバッグに入れて持ち歩きもOKです。
計測も、スイッチをパチリと入れるだけ。
あとは自動的に針が動いて、明るさを判定してくれます。
でも、なんだか難しそう…
○○ルクス(?)とかなんとか、よくわからないわ~
…という方。大丈夫です!
表示部分には、『団らん』『食事』『読書・勉強』『精密作業』の文字が。
数字の目盛りのほか、日本語表示で、今の明るさが何に最適な状況なのかバッチリわかるのです。
では、さっそく部屋の「明るさ」を測ってみることにします。
夜の我が家、照明はメインが蛍光灯、所々に白熱灯、という環境なのですが…
ショック!
というか、やっぱり、というか…
体験談の方々と同じく、明るさが全然足りていない、という結果が出てしまいました。
今これをパソコンで書いているまさにその場所、『精密作業』にあたる、いちばん明るさを必要とする状況ですが、判定はいちばん下の『団らん』レベル。
というわけで、実際に眼育明かりメータを使ってみると、『普段身の回りで使用している照明の明るさが十分でないことがわかって驚いた!』ということが、とても多いのです。
「測ってみたら、びっくりした」ということのワケや、「明るさ」=照明を点ければOKではない ことが、これでおわかりいただけたのではないでしょうか。
眼育明かりメータの詳細を確認する。※眼育明りメータは販売終了いたしました。
さらに…
眼育明かりメータ購入者には、特典がつきます!
非売品の限定冊子
読んで納得!「そうだったのか!? 明かりの秘密」(B5フルカラー/30ページ)
を、もれなくプレゼント!!
- 明るさと健康の関係
- ストレスと目の関係
- 明かりチャレンジクイズ
などなど、
今までどこにも載っていなかった、目からウロコ!のお話を、わかりやすいイラスト満載で解説。
ここでしか入手できない貴重な1冊です!
これがあれば、眼育明かりメータを完全に使いこなすことができます。
リビングで勉強、問題アリ??

ところで、お宅では、お子さんが勉強する場所はどこですか?
うちの子は宿題とか読書とか、ほとんどリビングでやってます…
というご家庭、案外多いのではないでしょうか。
確かに、自分の部屋で本人まかせにすると、ゲームやらマンガやら誘惑がいっぱい。
ちゃんとやってるのかしら…と、親としても気になりますよね。
その点、リビングなら目も届いて安心というもの。
ですが、ここで気をつけたいことがあります。
それは――
そう、「明るさ」なのですね。
ここで、眼育明かりメータの表示を見てみましょう。
団らん < 食事 < 読書・勉強 < 精密作業
こんなふうになっています。
右に行くほど、作業時に「明るさ」が必要である、ということ。
要するに、読書・勉強・パソコン・精密作業をする場合
⇒団らん・食事よりさらに明るくする
食事や団らんの場合
⇒逆に、読書・勉強のときよりも明るさを落とすことが、それぞれの状況にとって最適な”明かり環境”である、とされています。
それを考えると、食事や団らんを本来の目的とするリビングは、読書や勉強をする部屋よりもむしろ「明るさ」を落としたほうが良い
⇒そこで読書や勉強をするには、「明るさ」が足りないことになると言えるのです。
じゃあ、リビングの照明を明るく、読書や勉強に必要な「明るさ」と同程度にして、そこで勉強をするってことにすればいいのでは?
…と思われるかもしれませんね。
でも、それはちょっと問題アリ、なのです。
「明るさ」を抑えたほうがいい場合(?)
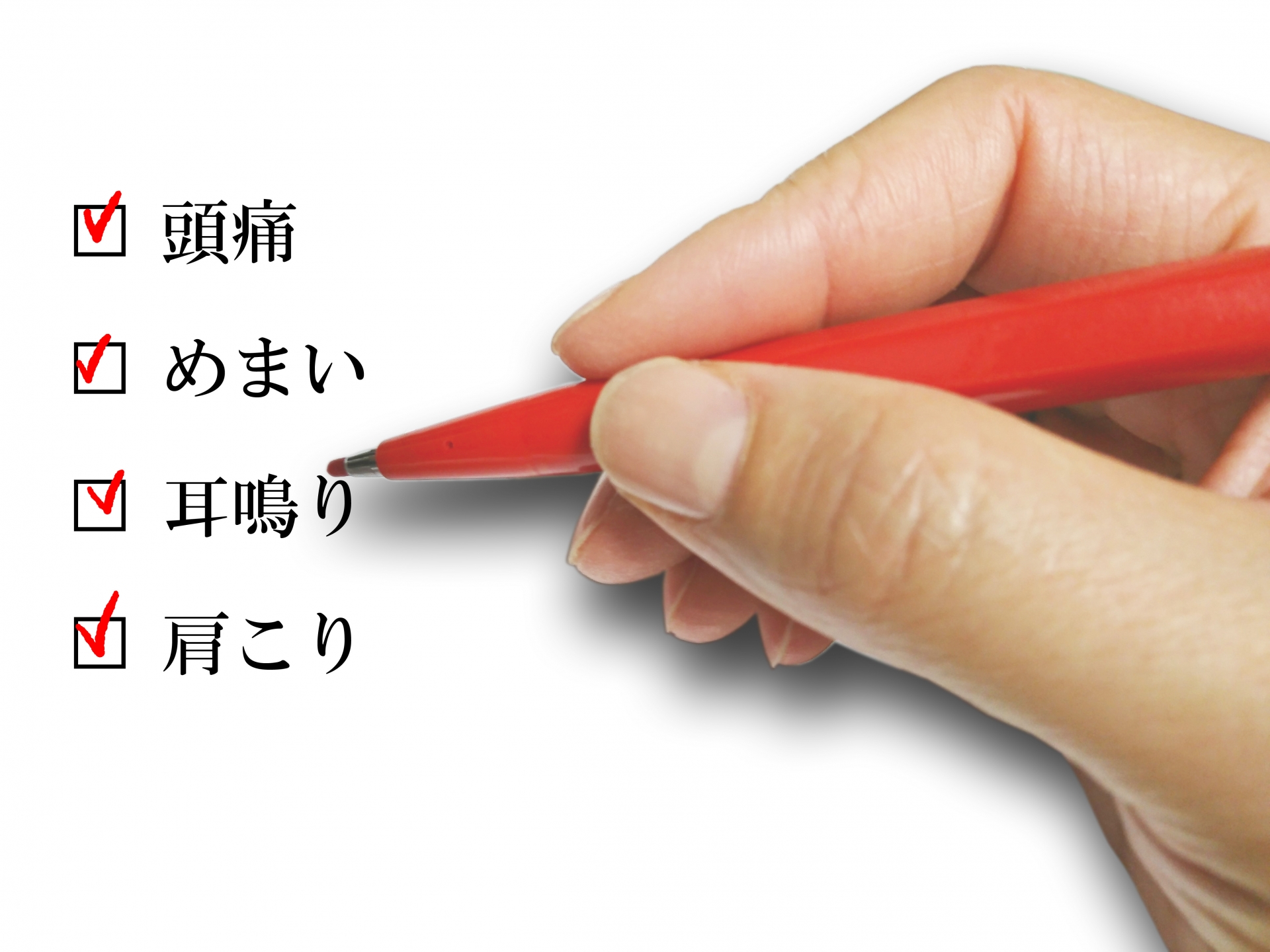
なぜかというと――人間は、自律神経というものを持っています。
これは体内の環境を整える働きをしていて、「交感神経」「副交感神経」の2つから成ります。
簡単に言うと、
「交感神経」 → 緊張感を保つ
「副交感神経」→ 心身をリラックスさせる
というように、互いに逆の働きをしながら、からだのバランスをとっているわけです。
このバランスが狂うと、身体や心にさまざまなトラブルが発生してきます。
基本的に明るい方が「交感神経」が有利になりやすく、暗い方が「副交感神経」が有利になりやすいという関係を持っています。
そのため、過剰な「明るさ」は、このバランスを崩す原因になってしまうのです。
食事・団らんといったくつろぎの場では、リラックスのために少し「明るさ」を抑えて、副交感神経を有利にする必要があります。
それに対して、読書、勉強、パソコン、細かい作業…などは、いずれも近くのものを長時間見る必要のある状況です。
ですから、明るさが足りないと、凝視になりがちになり、近視が発生しやすくなります。
一方、食事や団らんでは、近くのものを長時間凝視しなければならない状況ではありません。
したがって、目のために「明るさが足りない」状況には、なりにくいわけです。
このように、「明るさ」というのは案外奥が深く、視力の面以外にも、実は私たちの心身にいろいろと関わっていることです。
そして、単に「明るければすべてOK」というものではない、という側面があるのも、ちょっと意外だったかもしれません。
眼育明かりメータなら、
- それぞれの状況に必要な明るさ
- 今の明るさで不足か、または過剰か
ということが同時に、一目でわかります!
ちなみに、お子さんをリビングで勉強させたい、という場合は、テーブルの上で使える電気スタンドを用意してみてください。
手元に十分な明るさを確保することで、視力低下を防止できます。
ちなみに、普通の蛍光灯と比べて、目にやさしい明るさの質を持つ
は、下記で詳しくご紹介しています。
「机の上で同じコトをしていても、光の質によって目の疲れやすさに違いがあります。」
じんわり目を癒して、明るい視界で新年を!

さて、最後にもうひとつ…
いくら明るさを調整したといっても、長時間ゲームやDVD、パソコンなどに接するのはやはり、良くありません。
疲れ目から慢性的な眼精疲労となり、それが近視の原因になることがあるのはもちろん、からだのいろいろな部分に問題が起こってくることもわかっています。
お子さんだけでなく、お父さん・お母さんもなにかと多忙なこの時期、夜になると、なんだか目が疲れてショボショボする…と言うようなことはありませんか?
そこで、疲れ目に効果的なアイテムヒーリングアイピローの登場
目の疲労をとるには、温めるのが効果的。
ヒーリングアイピローは、ただ目の上に当てるだけでいいんです。
実は私も、1日の終わりに愛用しています!
内側のセラミック炭シートの働きでじんわり・ほんのりと温かくなるので、本当に自然な気持ち良さが実感できます。
使い捨てカイロなどのように温度が高くなるものだと、つけたまま寝てしまうのはちょっと不安ですが…
ヒーリングアイピローは、あくまでやさしい温かさで疲れ目を癒してくれるので安心。
気がついたら、つけたままぐっすり、ということもよくあります。
ズレ防止ストラップ付きだから、そんなことも可能なのですね。
ヒーリングアイピロー詳細を確認する。
まとめ

年末の今、1年中でいちばん暗くなるのが早い = 1日のうちで暗い時間が多い
気づいたら、子どもが暗い部屋でゲームやビデオ…となりがちな時期。
近視への第一歩を踏み出す可能性も高く、危険な季節です!
近い距離で細かいものを長時間見る場合は、「充分な明るさ」であることが、近視を進行させないために、とても大切
でも、食事や団らんなど、それ以外の状況では、心身のバランスを考えた際に、「明るさ」を適度に抑えたほうが良い場合もある
眼育明かりメータなら、
- それぞれの状況に必要な明るさ
- 今の明るさで不足か、または過剰か
ということが、一目でわかる!
目と心身の健康に役立つマストアイテム、ぜひご活用ください。
加えて、疲れ目を癒すヒーリングアイピローもプラスして、
年末年始も、ご家族の目とからだを健康に!!
そして――近視の対抗策として何より重要なのは”早期対処”。
ゲームの悪影響から近視が始まるその前に、できることがあったなら…?
「早期発見/早期対処」の機会を逃さないために…
視力ランドでは、無料で視力向上可能性判定を実施しております。
フォームに必要事項を入力するだけで、その場で瞬時に可能性を判定します。
お気軽にご利用下さい!
著者・監修者・運営情報
執筆
眼育総研事務局は、目の健康と視力ケアの情報サイト「視力ランド」を運営する編集部です。担当:太田(編集)
監修
監修範囲:医学的記述(一般的な症状説明・受診目安・注意喚起)
監修日:
運営
有限会社ドリームチーム
所在地:神奈川県横浜市青葉区田奈町43-3-2F / 連絡先:045-988-5123(視力ランド窓口):045-988-5124
表現設計について(薬機法・景表法・医療広告に配慮)
- 効能効果の断定(「治る」「改善する」等)は避け、一般的な情報と生活上の工夫に整理しています。
- 数値・作用機序に触れる場合は、一次情報(論文・公的機関資料)を参照し、出典を明記します。
- 症状が続く/強い場合は医療機関の受診をご案内します。
参考文献:本文末の「参考文献」セクションをご確認ください。
利益相反(COI):当記事には当社取扱商品の紹介が含まれる場合があります。
視力回復辞典(視力回復の真実)
おすすめタグ
人気記事ランキング

スマホが見えにくい…老眼の対策は“早めの対処”から|軽減のコツと環境づくり

子供の近視にショックを受けた親御さんへ|不安な気持ちと向き合う視力ケアの考え方

子どもの近視が将来の眼病につながる?──家庭でできるリスクを減らす対策

目は一生の資産——3分で整えるピント調節 “ピントフレッシュ”のすすめ

学校の視力検査A判定でも油断禁物—近視予防と『ホームワック』活用ガイド
関連記事

スマホが見えにくい…老眼の対策は“早めの対処”から|軽減のコツと環境づくり

子供の近視にショックを受けた親御さんへ|不安な気持ちと向き合う視力ケアの考え方

子どもの近視が将来の眼病につながる?──家庭でできるリスクを減らす対策

目は一生の資産——3分で整えるピント調節 “ピントフレッシュ”のすすめ

学校の視力検査A判定でも油断禁物—近視予防と『ホームワック』活用ガイド

自宅でできる視力回復トレーニング方法を徹底解説

スマホが原因で斜視に?増える”スマホ斜視”とその対策

眼科のワックは効果がないって本当?