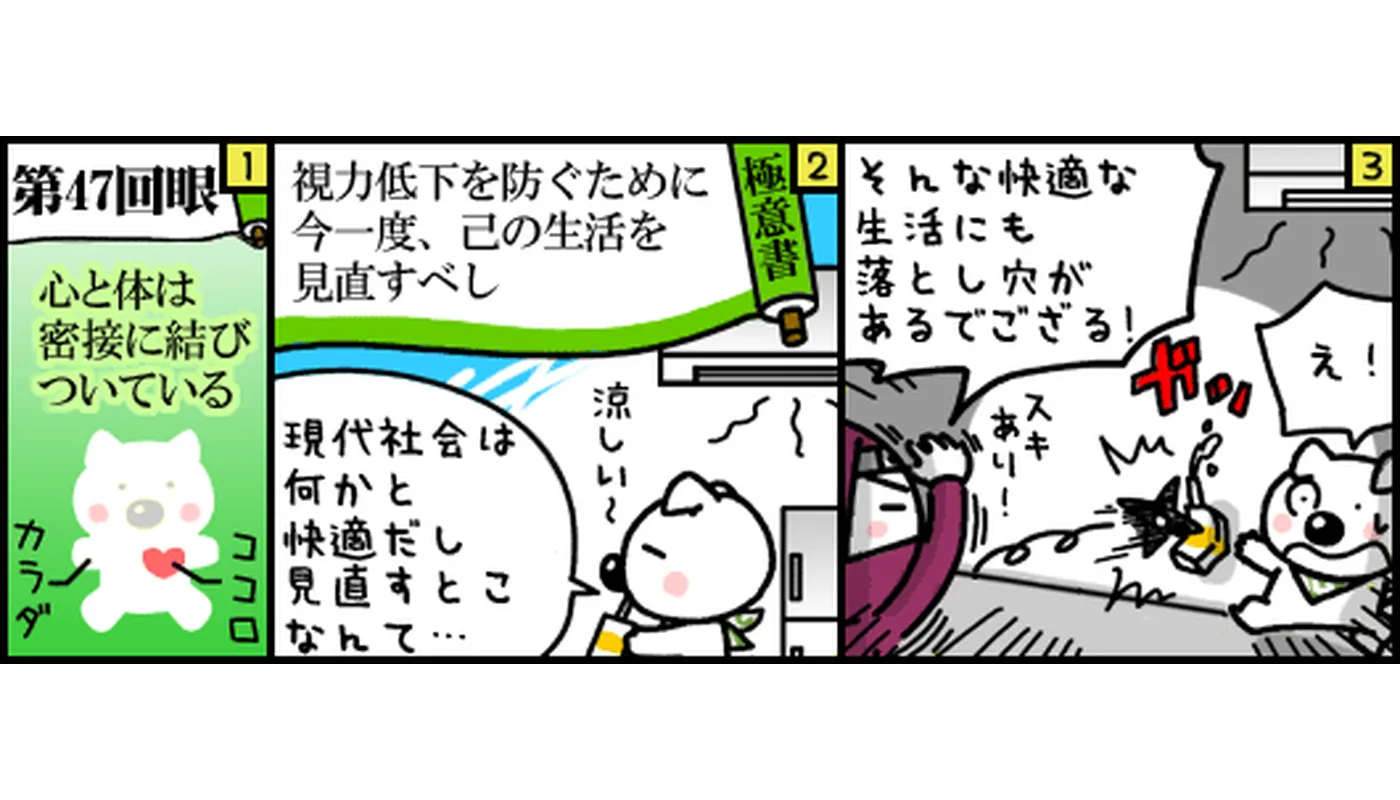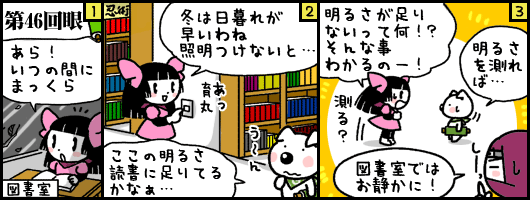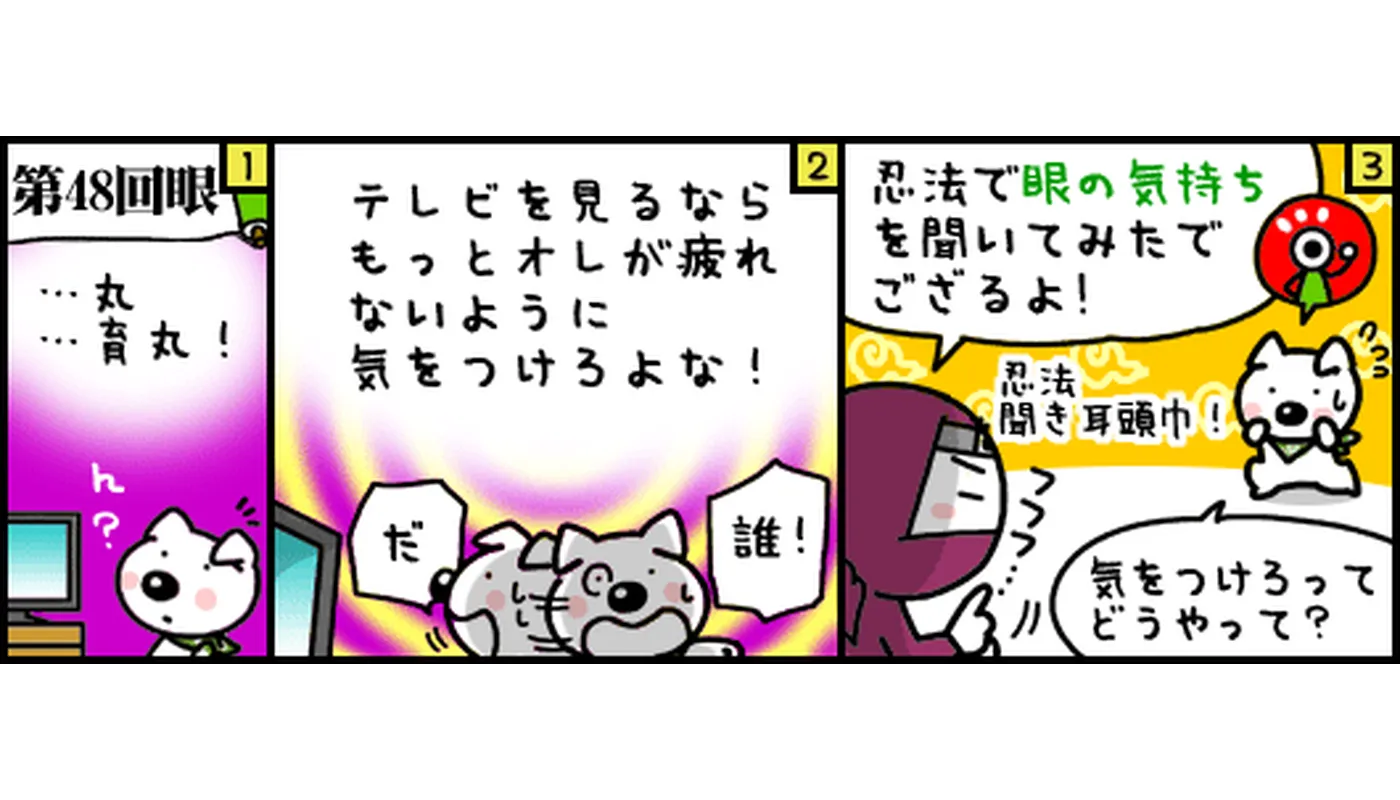はじめに

今年も、やってきてしまいました。
…そう、花粉症の季節です!
インフルエンザの流行も終わりきらないうちに、今年はいち早く花粉の飛散が始まったようです。
昨年からずっとマスクを手放せない、という人もいらっしゃることでしょう。
以前は、成人だけがかかるものと見なされていた花粉症。
ですが、ある製薬会社が16歳未満の子を持つ父母8,500人に行ったアンケートでは、3割以上の子どもが花粉症という結果が出ています。
近年では、乳幼児でも花粉症の診断を受けるケースもあると言います。
花粉症とはまさに、末長くつき合っていくものになりつつある、と言えるのかもしれません。
ここまで花粉症人口が増え、低年齢化を招いた要因には、スギ花粉の増加のほか、食生活の変化、大気汚染、ストレス…
など、現代人を取り巻く生活環境の変化があると考えられています。
昔はほとんどなかったのに、現代人の生活習慣から生まれ広がっていったという点では、近視にも似たものがあります。
そして、現代っ子に特有であるという意味では、“ストレス”もその1つ。
子どもたちが抱えるストレスと視力低下の関係について、このメルマガで取り上げたこともありました。
小学生のうちからあまりに忙しい生活を送る…など、子ども本来の姿とはかけ離れたスタイルが、ときに近視を後押ししてしまうこともある――そんな側面をご紹介しましたが、今回は、その続編とも言うべき内容をお送りしたいと思います。
現代っ子にふりかかる問題とは…
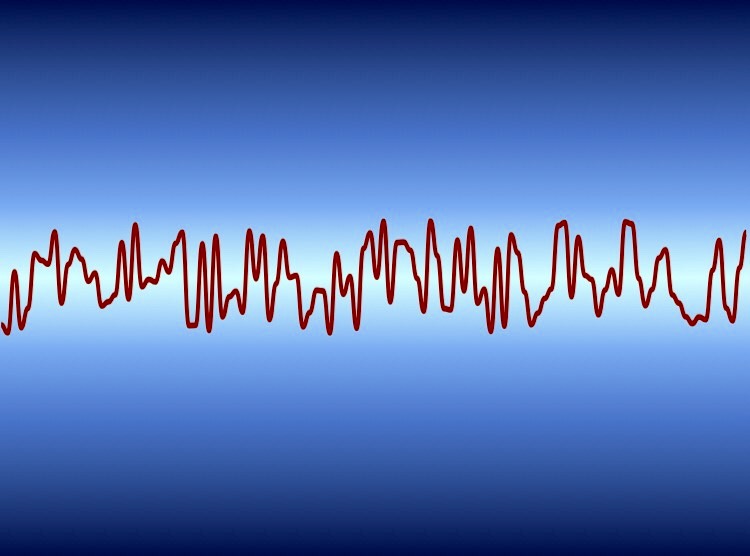
多忙な生活や人間関係の複雑な悩みなど、本来なら子ども時代には無縁のはずだったもの。
それらが日常生活に入り込むことにより、これまた本来子どもには無縁だったさまざまな問題が、現代っ子にふりかかっているわけです。
ストレスによる近視なども然り――。
子どものストレスに気づいたときに、親ができることとして
- おいしく楽しい食事の場をつくること
- 運動、入浴、そしてリラックスした睡眠を与えること
- 叱り方や指示のしかたを変えてみること
- 子どもの「いい部分」に着目して子どもにも伝えてあげること
- 外に出て、子どもといっしょに遊ぶ時間をつくること
このような点を、第44回では掲載しました。
意識して子どもと楽しく過ごす時間をつくったり、子どもへの接し方を工夫したり…
といった、主に精神面に配慮した“子どものストレス対処法”ですね。
このように、ストレスへの対処というと、大人子どもを問わず、精神面からのアプローチを考えることが多いように思います。
もちろんそれは重要なことです。
精神的な緊張 = ストレスが、からだの不調を引き起こすことは確かですから、それを和らげる工夫や方法を知っておくことは、健康の必須条件とも言えるかもしれません。
”ストレス”のもう1つの側面て?

忙しさや悩みなどが気持ちを張りつめさせ、結果的にからだにまで不調を生じる――というのが、これまでにお話した。
ストレスのかたちですが、このほかにも、気持ちの面からでなく、もっと直接的にからだにダメージを与える”ストレス”もあるということを、ご存じでしょうか?
家電製品と健康の関係(?)

人間の免疫機能にアプローチした医療を行っている医学博士の西原克成さんは、「1970年以降の生活の激変が、日本人の健康を変えた」と書いています。
高度経済成長時代を経て、私たちの生活を大きく変えたもの――それはなんと言っても、家電製品です。
戦前からすれば信じられないほどの便利さ・快適さをもたらしてくれたのが家電製品ですが、同時に、ここにもまた現代特有の問題が潜んでいた…
ということを、西原さんは指摘しています。
寒いときは寒さとともに、暑いときは暑さとともに暮らしてきたのが本来の人間です。
が、その部分がガラっと変わったことで、私たちのからだの状態までもが変わってきていると言います。
私たち現代人の生き方、生活の仕方が技術革命とともに変わってきました。
― 中略 ―
家電製品が発達したおかげで、冷たいものをたくさん摂取するようになりました。家庭用冷蔵庫とエアコンディショナーの普及で、いつでも冷たいものをとり、部屋を冷やすことが可能になりました。
とくに、夏になると頭が痛くなるくらい飲食物を低温にして、手足が冷えきるほどに部屋も冷やしたりすることが珍しくなくなりました。
ところが、冷たいものを摂取したり、皮膚を冷やして体温を下げると、細胞呼吸を担う、赤血球以外のすべての細胞内に存在するエネルギー代謝の小器官である
ミトコンドリアの機能がダメになるため、身体にはたいへん悪いのです。
(究極の免疫力 講談社インターナショナル刊)
冷たいものが与えるストレス

本来無縁だったはずのものが身近に存在するようになることで、健康にまで影響が及ぶようになったという点からすれば、これは、子どものストレス問題と根は同じだと言えます。
からだの内外を冷やし続けることは、知らず知らずのうちにからだの正常な機能を攻撃しているに等しい状態なのだそうです。
原因不明の慢性病も、冷えが元凶になっていることが、実はよくあると言います。
精神的ストレスが結果的にからだの不調を生じさせるとすれば、冷たいものの過剰摂取は、まさに直接的にからだにかかるストレスだと言えるでしょう。
このことは、まだ一般的に広く知られている、というところまでは至っていません。
それでも、人間のからだが本来持つ力 = 免疫力というものが見直される風潮が出てきている昨今、少しずつ認知され始めている情報でもあります。
からだのストレスになるほど、極端に冷やしすぎてしまう…という背景には、私たちの感覚、五感が鈍くなってしまっていることも関係していると言えます。
恒温動物である人間は、本来、一定の体温を保ち続けることで、からだの機能も正常に働かせられるようにできています。
このあたりのことは、凝視に偏った、本来的でない目の使い方が現代人の近視を増加させたということと端緒が共通していますが、現代生活の享楽と便利さに慣れきったことで、生き物としての本能を置き去りにしてしまった
――それが結果的に、自らストレスを与えることになっていると言えるでしょう。
”あたりまえ”を前提にしよう

とは言え、今さら文明生活から離れて暮らす、などというのはとても無理な話です。
今の生活の中で、できるだけからだにストレスがかからない習慣を心がけること。
それが、いちばん現実的ですぐにでも実践できる方法ではないでしょうか。
具体的には――
飲食物を冷やしすぎない
むしろ夏は要注意です。
冷蔵庫から出したものは、室温に戻してから口に入れることを習慣づけると、だいぶ違ってきます。
「冬こそコタツでアイスクリーム」など、自然に逆らった趣向や習慣もよくないのは言うまでもありません。
エアコンに頼りすぎない
地球温暖化対策でもよく言われる「冷房温度は28℃」を実行できればいちばん良いのですが――
それが無理でも、家族で過ごす場合はいちばん暑がりな人に合わせない、とか、エアコンを休ませる時間を必ずつくる、など、”夏は暑くてあたりまえ””冬は寒くてあたりまえ”を前提に、家族でルールを話し合ってみるのも良いですね。
”目だけ”じゃない視力の問題

今回お話した内容は、直接近視に結びつくわけではありません。
しかし、心のストレスが視力低下を引き起こす、ということからもわかるように、心とからだの機能にはとても密接な結びつきがあります。
視力の問題は、目だけに原因がある――のでは決してない、と言うことです。
それを前提にすると、からだの機能のひとつである「視力」を考えるとき、心を含めた、からだのあらゆる部分につながりがあり、それぞれが独立的に機能を果たしているのではないということをよく知っておいていただくことも、とても重要になってくるわけです。
心とからだ、そして生活習慣…
人間の営みは、すべてどこかでつながっているのですね。
まとめ
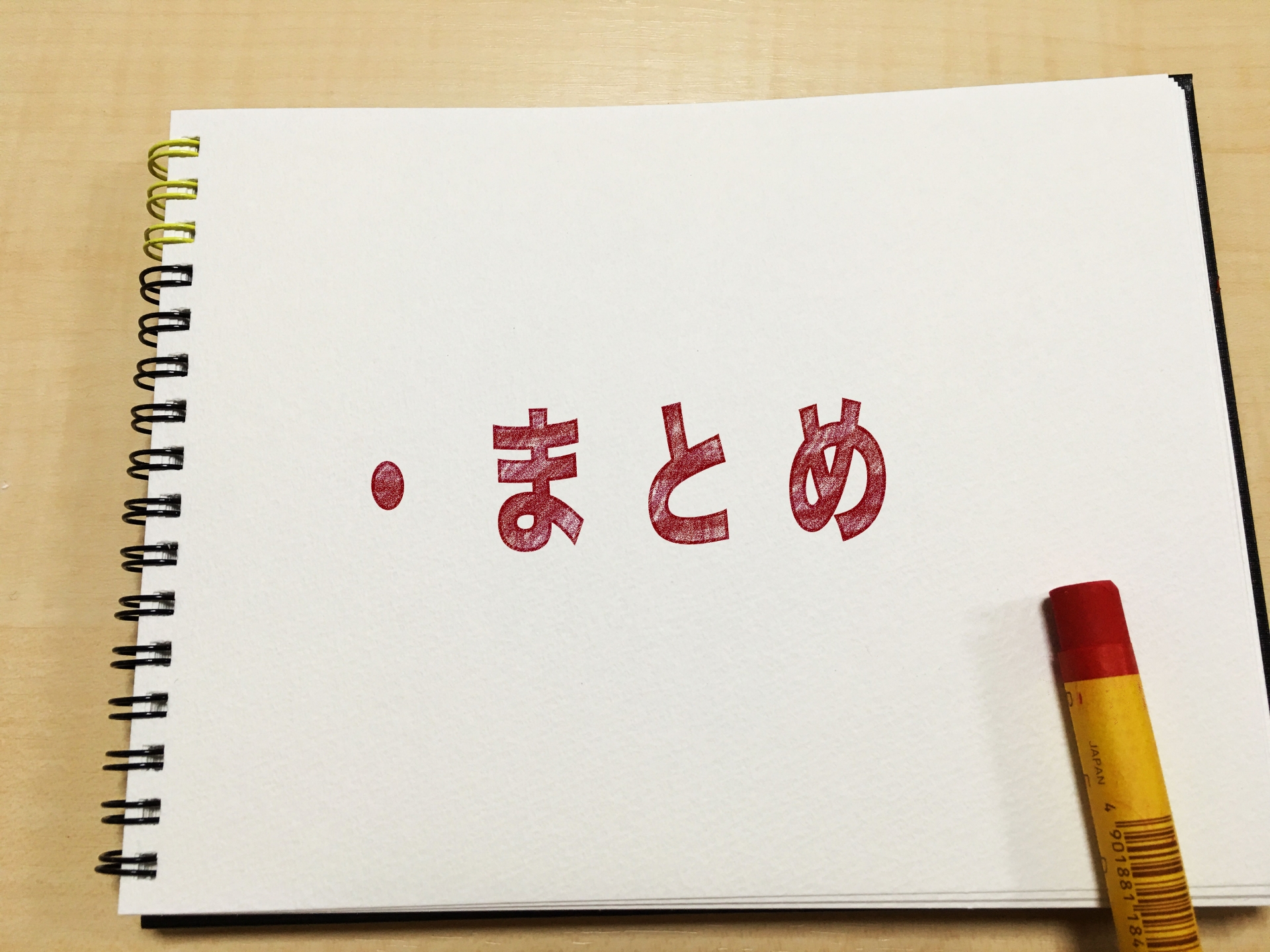
ストレスには、精神的な緊張が引き起こすもののほか、人間本来の生活習慣から離れたことでからだに生じてくるものもある
⇒心の悩みだけがストレスを引き起こすのではない
冷たいものの過剰摂取
⇒人間本来のものではない生活習慣が、からだにとってはストレスになる
- 飲食物を冷やしすぎない
- エアコンに頼りすぎない
など、極端な習慣をなるべくやめて”夏は暑くてあたりまえ””冬は寒くてあたりまえ”を前提に過ごしてみる
極端な生活習慣がストレスにつながる…
視力の悩みも視力だけの問題じゃない…ということに納得!
じゃあ、目のためにもなる生活習慣て、どんなこと?
うちの子のライフスタイル、どこが問題なのかしら…?
「早期発見/早期対処」の機会を逃さないために…
視力ランドでは、無料で視力向上可能性判定を実施しております。
フォームに必要事項を入力するだけで、その場で瞬時に可能性を判定します。
お気軽にご利用下さい!
著者・監修者・運営情報
執筆
眼育総研事務局は、目の健康と視力ケアの情報サイト「視力ランド」を運営する編集部です。担当:太田(編集)
監修
監修範囲:医学的記述(一般的な症状説明・受診目安・注意喚起)
監修日:
運営
有限会社ドリームチーム
所在地:神奈川県横浜市青葉区田奈町43-3-2F / 連絡先:045-988-5123(視力ランド窓口):045-988-5124
表現設計について(薬機法・景表法・医療広告に配慮)
- 効能効果の断定(「治る」「改善する」等)は避け、一般的な情報と生活上の工夫に整理しています。
- 数値・作用機序に触れる場合は、一次情報(論文・公的機関資料)を参照し、出典を明記します。
- 症状が続く/強い場合は医療機関の受診をご案内します。
参考文献:本文末の「参考文献」セクションをご確認ください。
利益相反(COI):当記事には当社取扱商品の紹介が含まれる場合があります。
視力回復辞典(視力回復の真実)
おすすめタグ
人気記事ランキング

スマホが見えにくい…老眼の対策は“早めの対処”から|軽減のコツと環境づくり

子供の近視にショックを受けた親御さんへ|不安な気持ちと向き合う視力ケアの考え方

子どもの近視が将来の眼病につながる?──家庭でできるリスクを減らす対策

目は一生の資産——3分で整えるピント調節 “ピントフレッシュ”のすすめ

学校の視力検査A判定でも油断禁物—近視予防と『ホームワック』活用ガイド
関連記事

スマホが見えにくい…老眼の対策は“早めの対処”から|軽減のコツと環境づくり

子供の近視にショックを受けた親御さんへ|不安な気持ちと向き合う視力ケアの考え方

子どもの近視が将来の眼病につながる?──家庭でできるリスクを減らす対策

目は一生の資産——3分で整えるピント調節 “ピントフレッシュ”のすすめ

学校の視力検査A判定でも油断禁物—近視予防と『ホームワック』活用ガイド

自宅でできる視力回復トレーニング方法を徹底解説

スマホが原因で斜視に?増える”スマホ斜視”とその対策

眼科のワックは効果がないって本当?