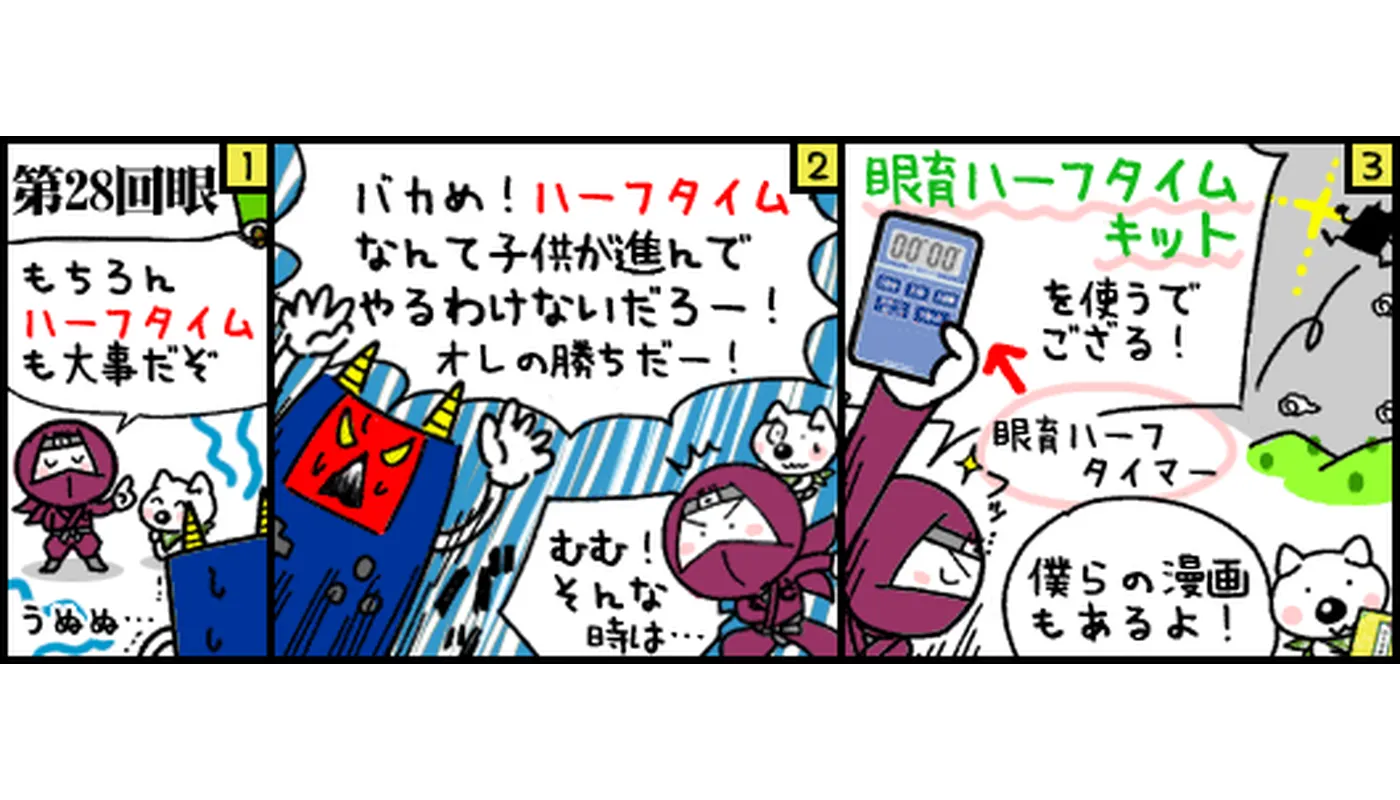【ステップ1】100円でできる対策
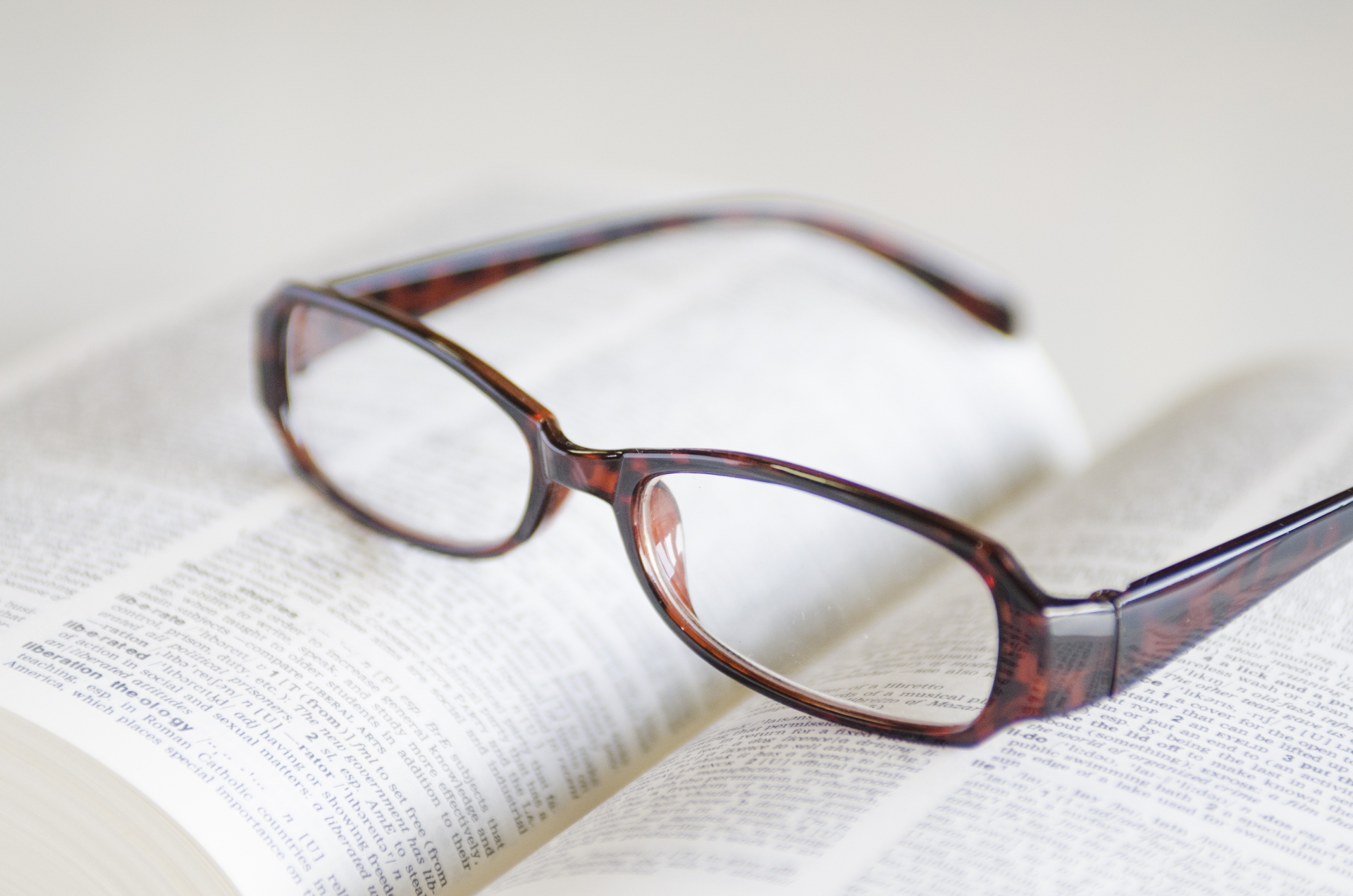
携帯型ゲーム機が子どもの生活に入り込み、視力にも悪影響を及ぼしている
それに対する策として、ライフスタイルや娯楽のあり方を考えてみることも必要
前回、そんなお話をさせていただきましたが――
具体的な対抗策を講じるためには、やっぱり子どもの自覚が必要。
携帯型ゲームが手強いのは、“携帯できる”アイテムだということ。
親が監視するには限界があります。
そこで今回お送りするのは、『子どもに自覚を持たせる《7つのステップ》』
子ども自身が、視力低下防止のための対策に取り組むようになるためには??
7つの方法やアイテムを、3回に分けて、ご紹介します。
親子のコミュニケーションにも役立つ話題がいっぱい!
ぜひご活用ください。
子どもに自覚を促すための対策として、まずはとても手軽ですぐに試せる方法を、ご紹介します。
まず、100円ショップに行きましょう。
そこで、老眼鏡(=遠視用メガネ)を入手します。
いちばん度の低い「+0.5」がベストですが、なければ「+1.0」のものを選んでください。
それを、お子さんにかけさせてみましょう。
そして、できたらそのまま外へ出かけてみます。
兄弟や友達の反応を見てみるのもよいでしょう。
せっかくですから、親自ら一芝居打ってみるのも手。
大袈裟なくらいに笑ってみせたり、鏡の前に立たせてみたり…
とにかく、周りが過剰なくらいに『反応』して、盛り上げるのがミソです。
これによって、「メガネをかけるということ」がどんなことか、子どもに体験させることができるのですね。
デメリットを感じるメリット

見た目以外にも、わずらわしさ、不便さ…など、実際体験してみなければわからない“メガネのデメリット”が、いろいろあるものです。
たとえば、メガネをかけたままお風呂に入ってみるというのも、おすすめの方法。
メガネはすぐに曇って前が見えなくなります。
日常生活の中の何気ない動作が、メガネをかけていることによってどれだけ不便に感じられるか…
ところで、老眼でもないのに老眼鏡(=遠視用メガネ)なんてかけて、大丈夫なの?? 害はないの??
そんな疑問を持たれる方も、いらっしゃるかもしれません。
ご安心ください。
近視の方が、わざとピントの合わないようにした遠視用メガネを20分間くらいかけ、調節ができない状態にして検査する方法があります。
これを『雲霧法(うんむほう)』といいます。
近くのものにピントを合わせた状態で固まってしまった眼の筋肉を、本来の状態に戻す目的で使われます。
ですから、近視の方が遠視用メガネをかけることで眼に悪影響があるということはなく、“メガネ体験”のために数十分程度かけておいても、問題はありません。
ただし、ピントは合わないため、車の通る道路に出るときは、外しましょう。
安全には、充分ご注意ください。
【ステップ2】”不便さ”でコミュニケーション

さて、子どもにメガネをかけることを体験させたら、それで終わりではありません。
ここからが、ステップ2の始まりです。
メガネをかけてみて、どうだったか
メガネを手放せない生活は、どれだけ不便か
など、“メガネ体験”からわかったデメリットを、親子で話し合ってみましょう。
親御さんが近視の場合は、より具体的な話ができるでしょう。
昔から視力が良くて、メガネの経験はない――そんな場合は、この機会に子どもと一緒に”メガネ体験”してみることをおすすめします。
自身で体験してみると、意外な発見が結構あるものです。
そういった“気づき”を話題にすることで、子どもと同じ目線に立ったコミュニケーションが可能になります。
こんな会話をしてみよう

たとえば、こんなポイントで話をしてみるのが、おすすめです。
1)鼻の上に余計なものを乗せることによる、不快感や違和感は?
動きが制限されてしまう――運動するとき、走るときはどんな感じか
肩が凝る感じはしないか
2)メガネをかけたままお風呂に入ってみてわかったことは?
すぐに曇ってしまう
頭や顔を洗うときには、じゃまになる
ほかには??
3)災害のときはどうなる?
とっさの行動をとらなければならないときの、メガネのハンデ
メガネなしで避難したとして、その先の生活は…?
4)海外旅行に行ったとき、メガネをなくしたら
国内では何とかなっても、海外では難しそう。
メガネひとつで、旅行の楽しさが台無し?!
5)男の子なら、ケンカのときは?(しないに越したことはないですが…)
手加減なしの待ったなし、という状況で、メガネだと…?
6)スポーツをするときは?
跑るとき、格闘技のとき
プロスポーツ選手になりたい!そんなとき、メガネは??
さらに、これはあってはならないこと、というのが前提ですが、
7)もし戦争が起こったら…?
「メガネに拘束される」ことがどんな結果につながるか…などなど、
メガネ体験によって実感したことに想像力をプラスして、会話を拡げてみましょう。
「想像力」の活用法

親子で想像力を働かせながら会話することは、子どもにとって、とても良い刺激になるものです。
普段想像力を失いがちな大人にとっても、良い訓練になる場合があります。
「他人の立場に立つ」ことが、日常生活や人間関係の中で大切なことはわかっていても、実際にはとても難しい場合がありますよね。
違う立場や経験を持つ人の気持ちになりきってみること――
“メガネ体験”は、ごく手軽にそれができる手段でもあります。
そして、想像力を加えながら会話を展開するための、糸口にもなります。
このような、テーマを持つ会話をすることによって、普段気がつかなかった子どもの成長に気がつかされたりするケースもあります。
コミュニケーションとは、『知恵と感情の交流』です。
そのことを意識して、子どもとのコミュニケーションを深めてみるとよいでしょう。
そして、子どもの中に「小さな自覚の芽」を発見したら、それを、認める→ほめる→そして育ててあげましょう。
口を酸っぱくして言い聞かせたり、無理矢理に約束事を守らせようとするやり方には、自ずと限界があります。
それよりも、親子の「話し合い」を上手に利用することによって、子どもの自覚を育てる方が実は効果は大きく、無駄な苦労も減るものです。
まとめ
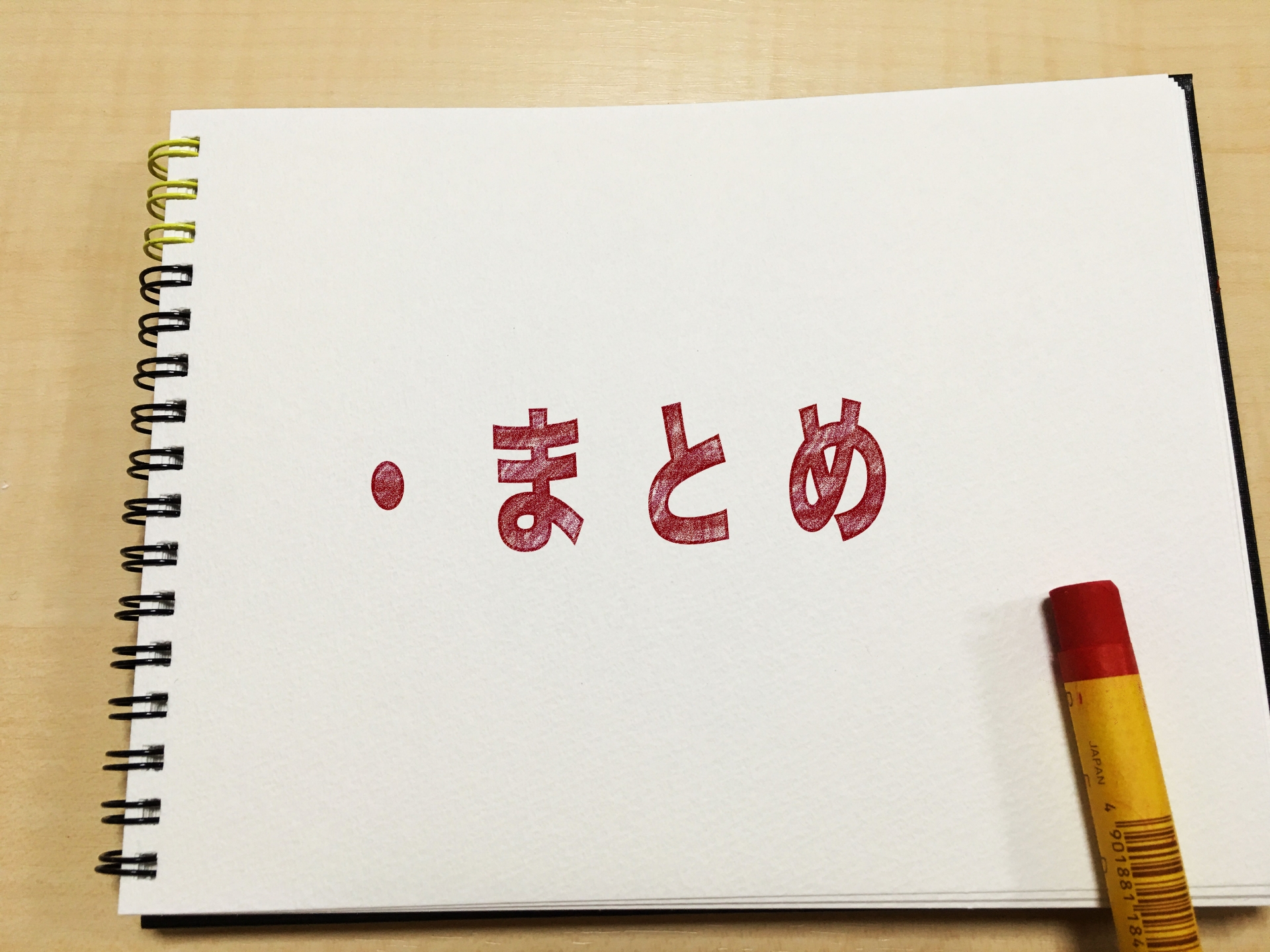
子ども自身に、視力低下防止の意識を持たせるために必要な《7つのステップ》とは…
ステップ1
「メガネをかけるとは、どういうことか」
を体験させる体感しないとわからない不便さ、デメリットは?
ステップ2
“メガネ体験”を糸口に、想像力を広げながら親子で会話を。
親子のコミュニケーションを深めましょう!
子どもの自覚は、認める→ほめる→そして育てるところから、始まります。
次は、『子どもに自覚を持たせる《7つのステップ》第2弾』
★ ステップ3~5をお送りします。お楽しみに!
“メガネ体験”で、メガネの不便さを親子ともども体感した!
改めて視力低下防止の大切さを実感。
でも、最近視力が落ち始めているみたい…
「早期発見/早期対処」の機会を逃さないために…
視力ランドでは、無料で視力向上可能性判定を実施しております。
フォームに必要事項を入力するだけで、その場で瞬時に可能性を判定します。
お気軽にご利用下さい!
著者・監修者・運営情報
執筆
眼育総研事務局は、目の健康と視力ケアの情報サイト「視力ランド」を運営する編集部です。担当:太田(編集)
監修
監修範囲:医学的記述(一般的な症状説明・受診目安・注意喚起)
監修日:
運営
有限会社ドリームチーム
所在地:神奈川県横浜市青葉区田奈町43-3-2F / 連絡先:045-988-5123(視力ランド窓口):045-988-5124
表現設計について(薬機法・景表法・医療広告に配慮)
- 効能効果の断定(「治る」「改善する」等)は避け、一般的な情報と生活上の工夫に整理しています。
- 数値・作用機序に触れる場合は、一次情報(論文・公的機関資料)を参照し、出典を明記します。
- 症状が続く/強い場合は医療機関の受診をご案内します。
参考文献:本文末の「参考文献」セクションをご確認ください。
利益相反(COI):当記事には当社取扱商品の紹介が含まれる場合があります。
視力回復辞典(視力回復の真実)
おすすめタグ
人気記事ランキング

スマホが見えにくい…老眼の対策は“早めの対処”から|軽減のコツと環境づくり

子供の近視にショックを受けた親御さんへ|不安な気持ちと向き合う視力ケアの考え方

子どもの近視が将来の眼病につながる?──家庭でできるリスクを減らす対策

目は一生の資産——3分で整えるピント調節 “ピントフレッシュ”のすすめ

学校の視力検査A判定でも油断禁物—近視予防と『ホームワック』活用ガイド
関連記事

スマホが見えにくい…老眼の対策は“早めの対処”から|軽減のコツと環境づくり

子供の近視にショックを受けた親御さんへ|不安な気持ちと向き合う視力ケアの考え方

子どもの近視が将来の眼病につながる?──家庭でできるリスクを減らす対策

目は一生の資産——3分で整えるピント調節 “ピントフレッシュ”のすすめ

学校の視力検査A判定でも油断禁物—近視予防と『ホームワック』活用ガイド

自宅でできる視力回復トレーニング方法を徹底解説

スマホが原因で斜視に?増える”スマホ斜視”とその対策

眼科のワックは効果がないって本当?