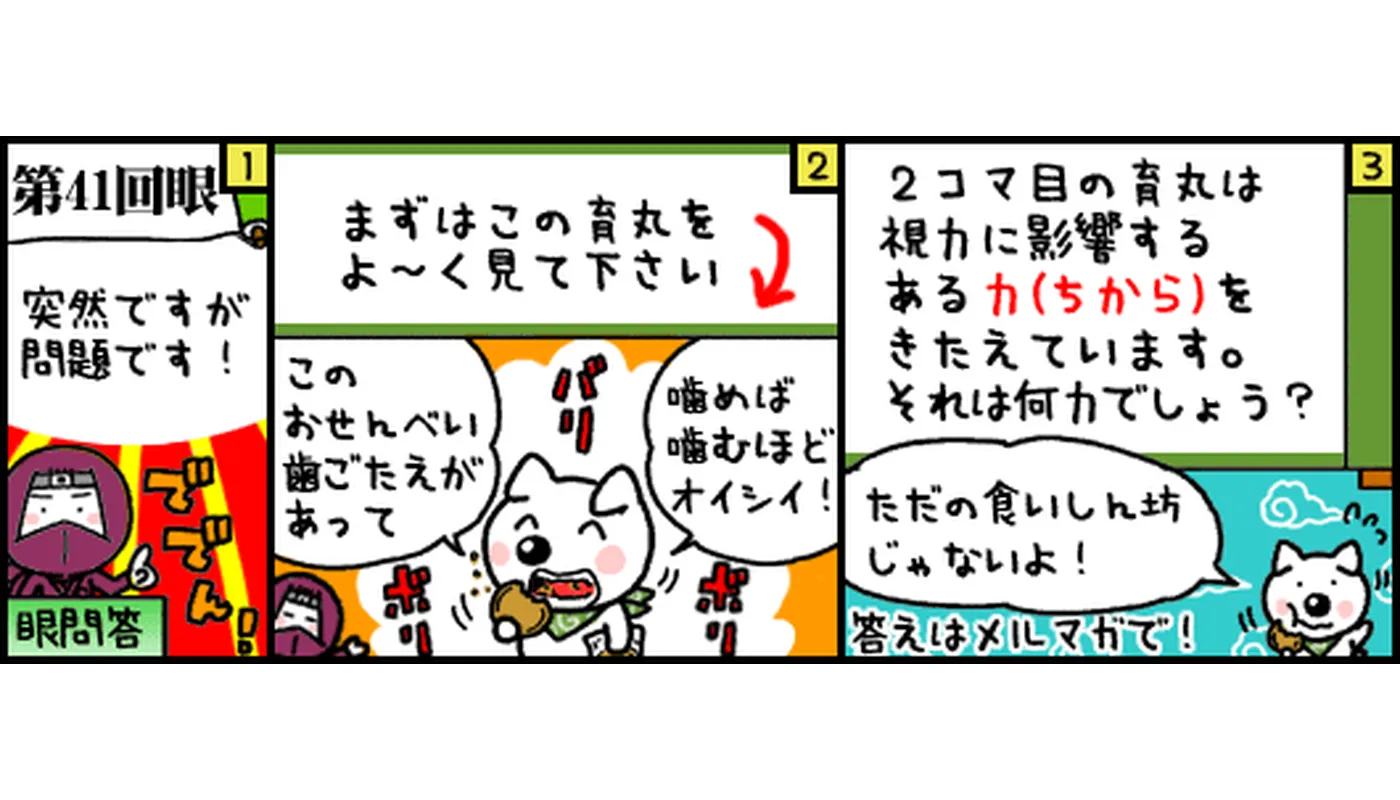はじめに

過去の新聞データベースを検索していて、こんな記事を見つけました。
『千葉県市原市の市立戸田小学校(児童数304人、林充校長)
昨春から、テレビを見たりゲームをしたりしない日を週に1日設ける
“ノーテレビ、ノーゲームデー活動”に取り組んでいる。
林校長は、
「テレビやゲームに長時間、接触している現状を心配していた。
ただ、テレビやゲームを否定するのではありません。
生活習慣を見直し、自制する力をつける試みです」
と話す。
当初は土曜日を想定したが、個々の家庭事情を考慮し、“曜日は問わず、週に1日。
できない場合は、時間をできるだけ減らす”と柔軟にした。
今年6月に取り組み状況を聞いたところ、”週1日以上実施した”家庭は68%に上り、”週1日以上時間を減らした”を含めると92%を占める。
毎週木曜日を“ノーテレビ、ノーゲームデー”にしている6年生男子は、「以前は、夜7時から9時ごろまでテレビを見て、その後にゲームをすることも多かった。
今は読書をしたり、家族で話したりする時間が増え、視力低下も止まった」』(読売新聞記事より)
このお子さんのコメントにも表れているように、テレビもゲームもない時間を過ごす機会を持つということには、非常に意義があります。
物心ついたときからテレビやゲームに囲まれているのが現代っ子です。
ほぼ生活の一部と化しているテレビやゲームを彼らから切り離すのは、至難の業でしょう。
“ノーテレビ、ノーゲームデー”を設けることは、視力低下防止の面からも大切な生活改善のきっかけづくりになります。
記事は、次のように続きます。
『“ノーテレビ、ノーゲームデー”を設けようという活動はNPO法人子どもとメディア(福岡市)が2000年に提唱、全国の小中学校、家庭などに広がった。
山田真理子代表理事(九州大谷短大教授=幼児教育)は、
「最近は、テレビよりゲームやインターネットなどが生活習慣を乱しており、映像メディア全般の影響を懸念しています」と説明する。
子どもたちの“映像メディア漬け”は深刻な状態が続いているようだ。
2004年の同団体調査(小学生~大学生約3,400人対象)では、平日6時間以上、テレビやビデオ、ゲームなどに接触している小学生は26%に上る。
午後9時前に寝る子どもは、小学4年生で4分の1、6年生は10分の1に過ぎない。
就寝が遅くなる主原因は“映像メディアとの接触”だった』
“映像メディア漬け”が子どもに与える悪影響は、視力低下のほかにもさまざまなことが指摘されていますよね。
それでも、こういった記事を読むにつけ「耳が痛い…」と思われるお父さん・お母さんは多いのではないでしょうか。
子どもの生活改善が簡単でない理由のひとつに、親も一緒に取り組まなければならない、ということがあります。
映像メディアが生活の一部になっているのは、子どもだけでなく親も一緒なのですね。
私なども、この話題に関しては反省しきりですが…
結局、子どもの生活改善は親自身の生活改善でもあるんだな、と再認識させられる話題でした。
記事に登場した6年生の男の子のように、毎週決まった曜日を「ノーテレビ、ノーゲームデー」にしてみたり、たとえば、毎日夜9時以降はテレビを消すとか、見たい番組を家族でピックアップして、それ以外はテレビを見ないとか――
何かひとつ、家族で映像メディアに接触しない機会をつくる工夫をしてみることは、とてもおすすめです。
雑音が介在しない中で、家族で一緒に過ごすことの楽しみも見つかるかもしれません。
さて今回は、『プールと目の関係』についてお話したいと思います。
歴史ある”常識”のウソ

学校でプールから出た後に、励行される習慣があります。
それは「目を洗う」ということです。
現代の子どもたちも、ひと昔前、もっと前…の子どもたちも、学校では“プール後洗眼”の指導を受けてきたと思います。
昔から、プールサイドの一角にはU型の水道があり、プールから出るとまずそこで目を洗うように、と言われたものですよね。
“プール後洗眼”は、それだけ歴史のある習慣だと言えます。
しかし、この習慣が目にとっては良くない影響を与えるという研究結果もあり、産経新聞でこんな記述で始まる記事が掲載されたこともあります。
『水道水の消毒に使われている塩素が角膜を傷つけ目に悪影響を及ぼすことを、石岡みさき医師(両国眼科)、慶応大学眼科などの研究チームが実験で明らかにし、米国の眼科学専門誌に発表した。
学校現場で当たり前に行われる水泳後の洗眼は、かえって目にダメージを与える恐れがあり、研究チームは「洗眼はやめてゴーグルで保護した方がいい」としている。』
”常識”を覆す根拠とは?

研究チームは、健康な男女各5人を被験者として実験を行いました。
- 体液と浸透圧が同じ生理食塩水
- 水道水
- 生理食塩水に塩素を加えたもの
この3種類を使って各自が眼を洗う、というのが実験の方法です。
結果は――
いずれも、目を洗う前と比べて角膜の傷がやや増えた
⇒塩素を加えたものを使った場合に、特にその度合いが高い
目を保護する粘液の成分が、水道水・塩素入り生理食塩水で洗ったときに減少
⇒生理食塩水の場合のみ、減らなかったというものでした。
さらに、角膜表面のバリア機能を調べる検査では、塩素入りの場合のみ低下が認められたという結果も加えられています。
記事のまとめには、次のように書かれています。
『塩素が目に悪影響を与える主な原因と結論付けた。
研究班の加藤直子・慶大非常勤講師は「強酸や強アルカリなどが目に入ったとき以外、目を洗う必要はない。
プール後の洗眼は、さらに傷を広げる可能性があるのでやめた方がいい」としている。』
つまり、
- 塩素によって、角膜に傷がつく
- たとえ体液に近いものを使ったとしても「目を洗う」ことによって、角膜を傷つけてしまう
- 水道水を使って洗うと、目の保護成分が洗い流されてしまうというダメージも加わる
という結果が出たわけです。
これが、今までの“常識”を覆す根拠になったのですね。
そもそも“プール後洗眼”は、厚労省がプール熱(発熱・結膜炎などを発症)の感染拡大を防ぐために呼びかけを始めたものです。
また、文科省も体育教員への指導手引で、水泳後の洗眼指導を例示しています。
これに対し、眼科医の間では“プール後洗眼”を問題視する声も上がっていました。
が、根拠となる研究が少なかったため、明るみに出なかった――というのが現状だったわけです。
逆効果のワケ

水道水と涙液は浸透圧が異なるため、角膜に障害を起こしやすい、という説を発表している眼科医もいます。
カップ状の容器を使って目を洗う洗眼液も市販されていますが、これが目にとっては逆効果である、という研究結果もあります。
洗眼液に含まれる防腐剤や界面活性剤が、涙液層を保持する”ムチン層”を洗い流してしまうため、ドライアイを進行させてしまう危険性がある――というのがその理由です。
つまり、目を洗うという行為は、「眼の表面を薄皮のように覆って守るはたらきをしている“涙”を洗い流してしまう。 そのため、かえって目を傷つけたり、乾燥させてしまったりするトラブルにつながりやすい。」ということなのですね。
とはいえ、プールの後に目が充血したり、ゴロゴロする感じがあったり、実際、塩素によって目の表面に傷がつくと、そんな症状が表れることがあります――といった場合、目を洗ってスッキリしたい…と思うときもあると思います。
そんなときは、小分けになっている使い切りタイプの目薬を使うのがおすすめです。
これは”人工涙液”と呼ばれるもので、涙に近い成分でできています。「目薬」とはいうものの“薬”というよりも、目を潤し、乾燥を防ぐ目的で使われます。
防腐剤も入っていないので(使い切りでないタイプの目薬には防腐剤が含まれています)、その点でも安心です。
が… やはり、人工のものに頼らずに済ませられるなら、それがいちばんです。 そのためにできることとは…? 次に、ご紹介していきましょう。
プールで目を守ってくれるのは…

“プール後洗眼”は逆効果である、ということが明白になってきたわけですが――それならば、洗う必要がないようにあらかじめ策を施しておく、という手が考えられます。では、プールに入るときに目を守るには、どうすればよいのでしょうか。
専門家の間でまず言われる対策は、新聞記事にもあったように、ゴーグルを使用するということです。
目を水に触れさせないようにすることが、いちばんの防御策なのですね。
スイミングスクールや一部の学校でも、ゴーグル着用を義務づけるケースが増えてきていると言います。夏休みになどにプールに遊びに行くときは、ゴーグルを持参しましょう。
ただし、ゴーグル使用に関しては注意事項があります。まずは、きちんとサイズの合ったゴーグルを使用することです。
あるゴーグル製造メーカーの調査によると、成人と小学校高学年の子どもを比較すると、左右の目の間の距離(瞳孔間距離)は約4ミリ、頭囲は27ミリの差があるのだそうです。
また、3歳と9歳の子どもでも、瞳孔間距離4.5ミリ・頭囲3.5ミリの差があるといいます。
サイズの合わないものは水漏れの原因になるので、要注意です。
さらに、サイズが小さいものを使って、目の周囲を締めつけてしまうのも良くありません。眼球を圧迫することが目のトラブルにつながることもあるのです。
目のバリアって?

ゴーグルを使うことのほかに、もう1つ有効な対策があります。それは、体にもともと備わっている機能を活用する、というものです。人間の体には、自浄作用や免疫機能があります。
それらがさまざまなトラブル要因から体を守るバリアの働きをしていることは、皆さんもご存じの通りだと思います。
目の場合、そのバリアにあたるのが”涙”です。眼球の表面は、常に涙の薄い膜で覆われています。
目にゴミが入ったときなど、自然に涙があふれてきて、異物を外に出そうとしますよね。そのほかにも、涙には感染を防ぐ働きや、傷の治癒を補助する働きがあるのです。
プールに入っても少々のことでは病気に感染しないのも、塩素のダメージをもろに受けずに済むのも、涙のバリア機能が働いてくれているおかげなのですね。
ですから、涙がきちんと機能するようにしておくことは、ゴーグルと同じくらい…それ以上に大切なことなのです。
生活習慣がモノを言う

でも、涙がきちんと機能するようになんて、そんなの当たり前のことでしょ?…と思った方、ちょっと待ってください。
近年、その“当たり前”の涙をからす大敵が現われているのです。
皆さんも耳にしたことがあると思いますが、「ドライアイ」などと呼ばれる症状が、それです。
スマホ・ゲーム・タブレット・パソコン・テレビなどのモニター機器に囲まれて暮らす現代人。そんな私たちは、とても“凝視”をしやすい環境におかれている――ということは、常々お伝えしている通りです。凝視することでまばたきが減り、涙が少なくなって目が乾く、という現象が起こります。
本格的な「ドライアイ」の症状は、光を眩しく感じたり目に痛みを感じたり、目がゴロゴロしたり…といったものです。
が、モニター機器に長時間接したあとに、何となく目が乾燥するな、と感じたりすることがあれば「ドライアイ」予備軍といえるでしょう。
凝視することは近視を引き起こす一要因でもありますが、こんな弊害もあったのですね。これを防ぐためにモノを言うのは、普段からの生活習慣です。
冒頭でご紹介した“ノーテレビ、ノーゲームデー”を実行してみたり、眼育総研がおすすめする目の休憩『ハーフタイム』を生活に取り入れたり、お子さんと一緒に、涙を涸らさないための工夫をしてみてくださいね。
まとめ
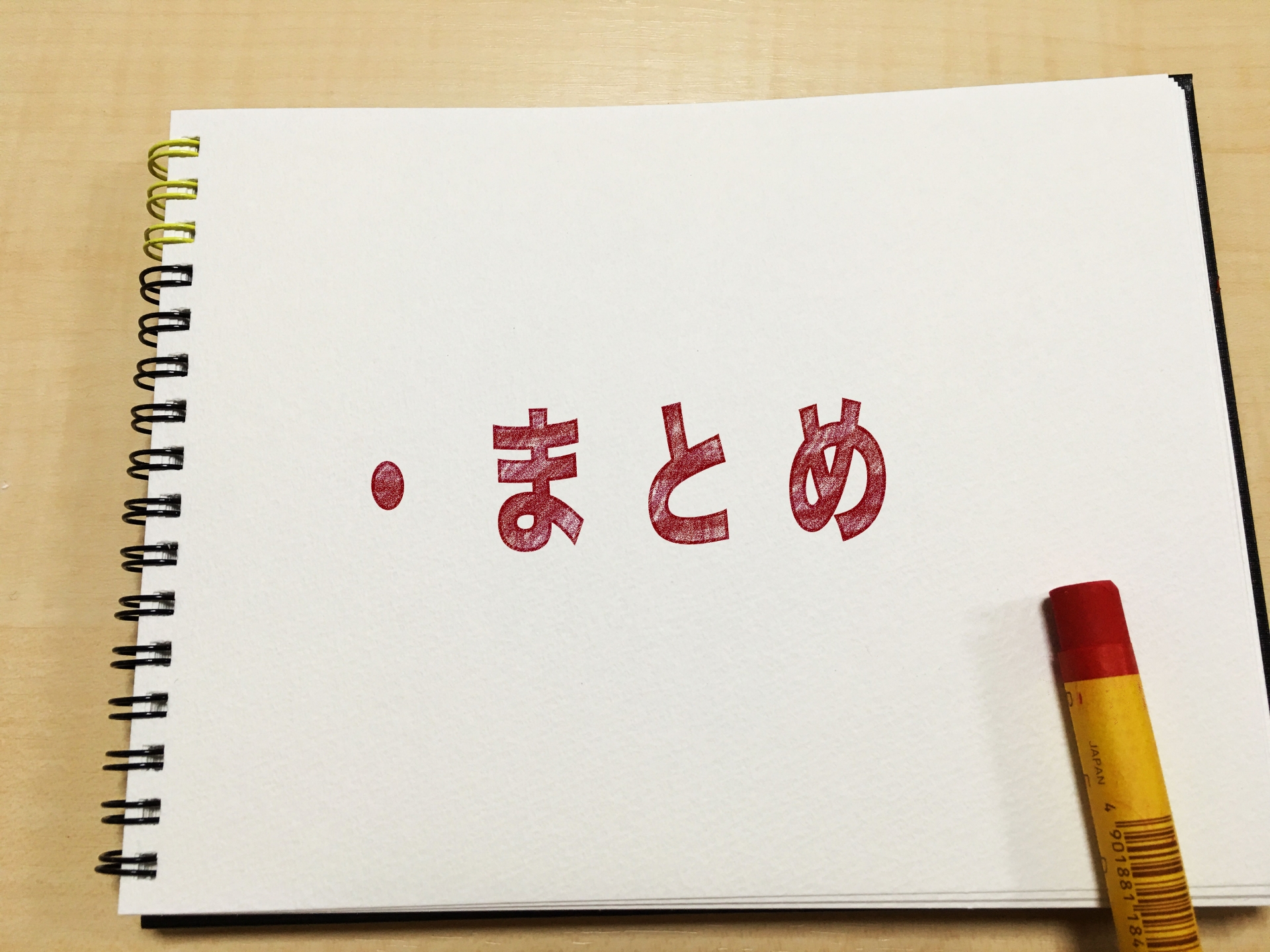
“プール後洗眼”は、目に悪影響あり
プールではゴーグル使用が◎ ⇒ただし、顔のサイズに合ったものをきちんと選ぶことが大事!
プールでの感染や、塩素による目のダメージを防ぐには、涙による自然治癒力で対処しよう! ⇒普段から、ドライアイなどを防ぐため“凝視”をしない生活習慣を
涙の機能と凝視をしないことの大切さがよくわかった! もっと、目に良い生活習慣をアドバイスしてほしい…
「早期発見/早期対処」の機会を逃さないために…
視力ランドでは、無料で視力向上可能性判定を実施しております。
フォームに必要事項を入力するだけで、その場で瞬時に可能性を判定します。お気軽にご利用下さい!
著者・監修者・運営情報
執筆
眼育総研事務局は、目の健康と視力ケアの情報サイト「視力ランド」を運営する編集部です。担当:太田(編集)
監修
監修範囲:医学的記述(一般的な症状説明・受診目安・注意喚起)
監修日:
運営
有限会社ドリームチーム
所在地:神奈川県横浜市青葉区田奈町43-3-2F / 連絡先:045-988-5123(視力ランド窓口):045-988-5124
表現設計について(薬機法・景表法・医療広告に配慮)
- 効能効果の断定(「治る」「改善する」等)は避け、一般的な情報と生活上の工夫に整理しています。
- 数値・作用機序に触れる場合は、一次情報(論文・公的機関資料)を参照し、出典を明記します。
- 症状が続く/強い場合は医療機関の受診をご案内します。
参考文献:本文末の「参考文献」セクションをご確認ください。
利益相反(COI):当記事には当社取扱商品の紹介が含まれる場合があります。
視力回復辞典(視力回復の真実)
おすすめタグ
人気記事ランキング

スマホが見えにくい…老眼の対策は“早めの対処”から|軽減のコツと環境づくり

子供の近視にショックを受けた親御さんへ|不安な気持ちと向き合う視力ケアの考え方

子どもの近視が将来の眼病につながる?──家庭でできるリスクを減らす対策

目は一生の資産——3分で整えるピント調節 “ピントフレッシュ”のすすめ

学校の視力検査A判定でも油断禁物—近視予防と『ホームワック』活用ガイド
関連記事

スマホが見えにくい…老眼の対策は“早めの対処”から|軽減のコツと環境づくり

子供の近視にショックを受けた親御さんへ|不安な気持ちと向き合う視力ケアの考え方

子どもの近視が将来の眼病につながる?──家庭でできるリスクを減らす対策

目は一生の資産——3分で整えるピント調節 “ピントフレッシュ”のすすめ

学校の視力検査A判定でも油断禁物—近視予防と『ホームワック』活用ガイド

自宅でできる視力回復トレーニング方法を徹底解説

スマホが原因で斜視に?増える”スマホ斜視”とその対策

眼科のワックは効果がないって本当?