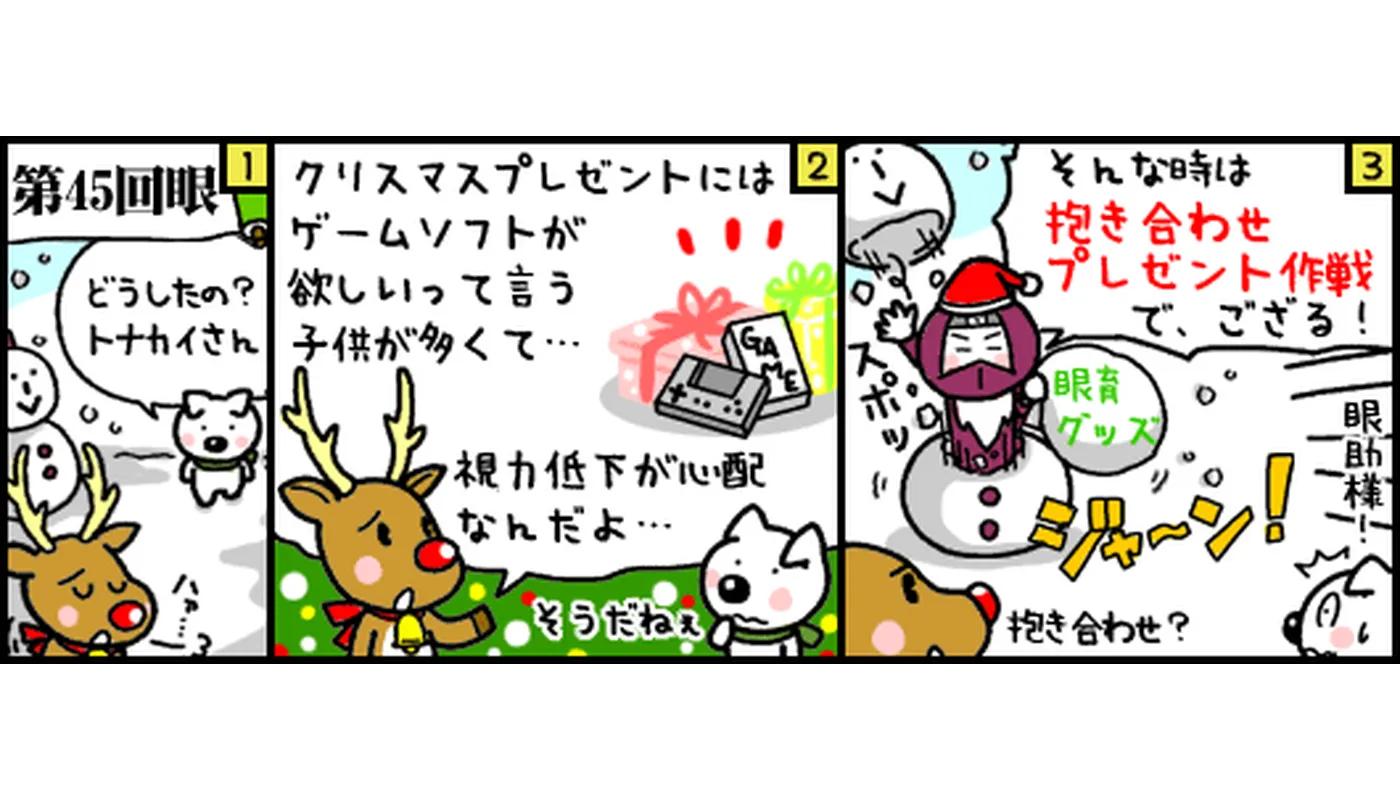はじめに

新聞のデータベースで、ある特集記事を見つけました。
そのタイトルがちょっと目を引くものだったので、かなり印象に残りました。
その名も、【溶けゆく日本人】(産経新聞より)
思わず「えっ?」と目をとめてしまうこのタイトル、記事の内容は、現代日本人に起こっている身近な問題を取り上げたものでした。
サブタイトルには『快適の代償』とあり、快適さの裏にある諸問題に焦点を当てています。
その最終回『眠れぬ子供たち 夜型生活の”犠牲者”』という記事の一部分を、ここにちょっと紹介します。
「不眠の波は子供たちにまで押し寄せてきている」という出だしで、中学受験を控えたある6年生の女の子が、「朝、眠くてなかなか布団から出られない」状況に陥っている事情を説明する内容なのですが――
「1日のスケジュールはこうだ。
放課後、学校の門を出ると母親が車で迎えにきており、そのまま塾へ。
午後9時すぎまで授業 ⇒ 帰宅の途につくのは10時すぎ。
夕食は母親が用意した『塾弁』(塾で食べる弁当)で済ませている。
午前0時前に寝られることはほとんどない。
友達との会話についていくため、ビデオにとったテレビドラマを早送りしながら見て、床に就くのが2時近くになったこともある。
『朝もつらいけれど、一番しんどいのは、(眠気が襲う)5時間目と6時間目の授業中。
1、2時間目が体育や音楽の日は、家でゆっくり寝て3時間目から学校に行くときもある。
学校に遅刻してもお母さんは怒らない。
受験まであと2ヶ月だし…』」(一部省略)
この続きとして「そんな子供たちが勉強時間と引き換えに犠牲にしているのが、遊びや読書、一家団欒の時間、そして睡眠だ」とあり、“寝る間を惜しんで”やらなければならないことがいっぱい、という生活を送るうち、睡眠障害に陥る子供が増えていると記事は指摘しています。
小学生のうちからこういう生活を送る子供が、全体的に「増えている」のかどうかはわかりません。
が、大人同様、子どもにも少なからず“夜型生活”の影響が出ていることは、否めないでしょう。
また、記事では触れられていませんが、こういった生活スタイルが多大なストレスをもたらすことも確かです。
記事を読んで感じるのは、単に“忙しい”ということ以外にも、子どもにとってのストレスの要素が垣間見えるということです。
「友達との会話についていくため、ビデオにとったテレビドラマを早送りしながら見て…」というくだりなどは、現代っ子の事情をよく表しているのではないでしょうか。
これだけ多忙でも、人づきあいもおろそかにはできない…
と言った子どもの事情を考えると、まさに大人のストレス社会の縮図を見るような気になります。
このようなストレスから、さまざまな問題が子どもの身に起こっている――
と言えるわけですが、実は、近視にもその側面が大いに関係しています。
以前、『ストレスが目に与える多大な影響』について少しお話ししましたが、今回はその部分をさらに掘り下げ、目とストレスの密接な関係について考えてみたいと思います。
度のないメガネで視力が…?
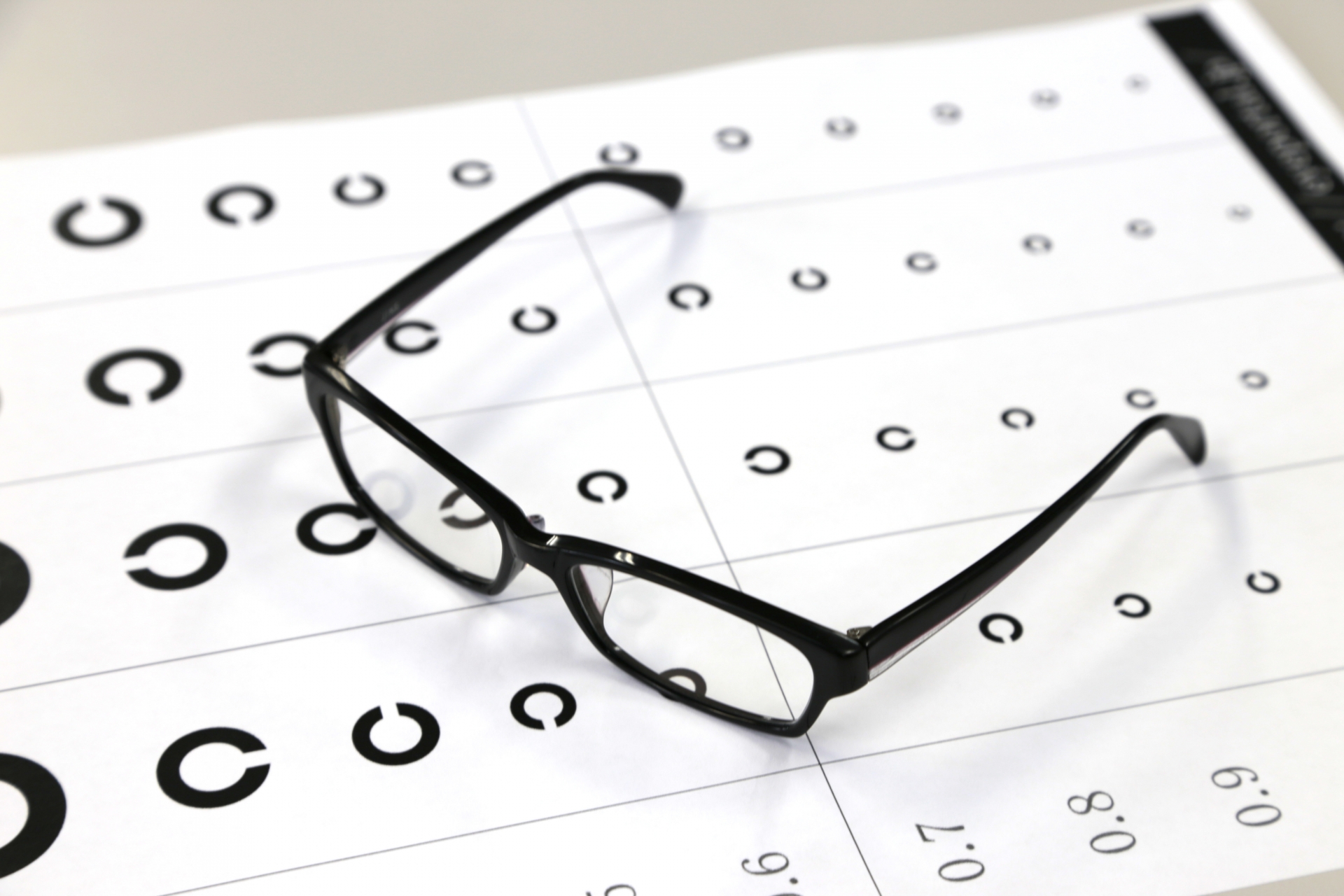
ストレスの多い環境が視力低下と関係することは、以前も触れました。
最近では、この“ストレスと視力低下”について、専門家の間でもずいぶん問題意識をもって取り上げられるようになってきています。
『日本眼科医会』のHPにも、子どもの目の心身症―心因性視力障害と題する、次のような記述があります。
「目には悪い所がないのに視力が落ちたり、また近視、遠視、乱視などでメガネをかけても視力が良くならない小学生や中学生が増えています。
ものを見るために目は重要ですが、最終的にものを見ているのは脳なのです。
この脳にストレスがかかると、目に見えているはずのものが認識できないことがあります。
これが心因性の視力障害です。
8歳から12歳の子どもに最も多くみられ ――中略――
男女差があり、女子は男子の3~4倍多くみられます。
視力は悪いにもかかわらず、眼球自体には異常は発見されません。」
こういったタイプの視力低下は、0.4~0.6程度の比較的軽いものであることが多く、学校検眼で見つかるケースが大半なのだそうです。
続いて、「このような子どもをよく調べてみますと、学校や家庭で心の悩みを抱えていることがあります。
このストレスが、視力障害の原因と考えられています。
視力を測定してみますと、測定のたびごとに視力が違っていたり、度のないメガネをかけると、視力が改善することもあります。」とあるのですが、【度のないメガネをかけると視力が改善する】という部分など、思わず読み返して確認したくなります。
「度のあるメガネ」の間違いじゃないの??
…と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、これは間違いではありません。
まさに、視力がストレスの状態に左右される、というケースがよくわかる話なのですね。
うちの子と似てる??

続いて、具体的な子どものストレスのケースも挙げられています。
「たとえば家庭内では、肉親の死、両親の不仲、離婚、親の愛情の差別、塾通い、お稽古ごとの負担、親の過干渉、などです。
また学校関係では、入学・転校、クラス・担任替え、友人関係、部活、などがあります。
試験になると答案が見えないとか、ピアノの稽古のときに楽譜が見えない、算数の時間になると黒板の字が読めないなど、時と場所によって見えないこともあります。
心因となる要因はさまざまです。」
これらのケースを見て、
「なんだかうちの子と状況が似てる…」
と思われたお父さんやお母さんも、いらっしゃるかもしれません。
そのくらい身近で、誰にも思い当たりそうなことが多いのではないでしょうか。
眼育総研でも、皆さまからの『近視お悩み相談』にお応えする際には、お子さんの視力低下に関して“ここ最近ストレスを感じるような状況がなかったか?”を伺っています。
今までに実際にあったご回答のパターンとして、
- 海外に引っ越した
- 転校して、なかなか馴染めないようだ
- 下の子が生まれ、今までのように親がかまってやれなくなった
- 習い事が多い
- 習い事や塾の「試験」があり、緊張することが多い
- 小学校・中学校受験の勉強をしている
などがあります。
これらを見ても、やはり先述のパターンと似通っているものが多いことがわかります。
「のんびりしたい」子ども(?!)

ベネッセコーポレーションが数百人の小学生を対象に行った、『モノグラフ・小学生ナウ』という調査があります。
その結果を見ると、現代っ子の生活が過密でストレスフルなことが浮き彫りになっています。
「もし2時間くらい暇ができたらやりたいこと」
という調査項目では、こんな結果が出ています。
| (%) | (やりたい) | (やりたくない) | (わからない) |
|---|---|---|---|
| 友だちと外で遊ぶ | 76.3 | 15.5 | 8.2 |
| 好きな本をのんびり読む | 66.8 | 24.5 | 8.7 |
| のんびりテレビを見る | 53.4 | 40.3 | 6.3 |
| のんびりマンガを読む | 54.4 | 37.1 | 8.5 |
| 友だちと室内で遊ぶ | 44.7 | 45.2 | 10.1 |
| 予習か復習をする | 25.9 | 60.2 | 13.9 |
好きな本をのんびり読む、のんびりテレビを見る…などまるで、中高年サラリーマンの調査かと見まごうばかりです。
昔は、暗くなるまで外で遊び、疲れて眠る、というのが子どもの当たり前の姿でした。
「のんびりしたい」などという発想自体、子どもが持つこともなかったものです。
友達と外で遊ぶ、という項目に「やりたい」と答えた人数が多いのは、必ずしも普段できていないからという理由ではないかもしれません。
が、ここまで見てきたような子どものストレス要因を考えると、2時間というまとまった時間を外遊びに割くことは、難しくなっているとも言えそうです。
また、冒頭でご紹介した新聞記事の女の子のような生活を続けていれば、それを切望するようになるのも無理からぬ話だとも思えます。
ストレスと目の本当の関係

では、なぜストレスが視力低下につながるのか、ということですが、先にご紹介したHPの記述に、
脳にストレスがかかると、目に見えているはずのものが認識できないことがありますとありました。
これが、強いストレスが視力低下を引き起こす1つの理由だと考えられているのですね。
さらにもう1つ――
辞書で”ストレス”を引くと、
「寒冷・外傷・精神的ショックなどによって起こる精神的緊張や生体内の非特異的な防衛反応。
また、その要因となる刺激や状況。」
(大辞泉より)とあります。
要するに、ストレスとは、外的要因が引き起こす精神的かつ肉体的な”緊張”であるわけです。
よく、緊張してガチガチになる、などと表現することがあります。
実際、緊張すると人間の体はかたくなりますよね。
体に力が入り、筋肉をゆるめることができなくなってしまうことがその原因ですが、これは、目に関しても一緒です。
目の筋肉に力が入りすぎると、遠くのピント調節ができなくなります。
そのようなタイプの視力低下を、「調節緊張」と呼ぶことがあります。
調節緊張は、近くのものを凝視し続けたために起こることが多く、その場合も、目にとっては長時間”ストレス”を強いられた結果であるといえるわけです。
ストレスと目の密接な関係が、おわかりいただけたかと思います。
カギは、「目の○○○」

以上のようなことを考えると、もはや、子どもであっても日常的なストレスと無縁ではいられないと結論づけざるをえない状況――と言えそうです。
でも、逆に考えると、人間にとって全くのストレスフリーという状況はありえない、とも言えます。
現代のストレスが平和な時代ならではのものだとするなら、そうでない時代のストレスも、当然あったはずです。
そうなると、まず大切なのはストレスを排除しようとすることではなく、ストレスへの対抗力を養っておくことだと言えます。
目に関することに限って言えば、ストレスがかかりにくい状態を普段から養っておくことが、重要なのです。
そのためには、どうすればいいか??
――答えは、一言でいうなら「目の使い方」を改善する、と言うことです。
ストレスに強く近視になりにくい目というのは、その使い方にカギがあります。
良い視力を維持する人は、無意識のうちに“良い「目の使い方」”を身につけています。
ですので、それを見習い、同じように身につけてしまえば良いことになります。
日常生活がモノを言う

では、その近視になりにくい「目の使い方」とは――?
とにかく、”凝視”をしない、ということに尽きます。
近い距離の狭い範囲を”凝視”し続けるということが、目にとっては最も酷使している状態になります。
“凝視”とは対極にある良い「目の使い方」を、眼育総研では“眺視” (ちょうし)と呼んでいます。
眺視について、以前詳しくお伝えしましたので、下記をご参照ください。
凝視(ぎょうし)をやめて、<眺視(ちょうし)>をしよう!
目が緊張状態に陥らない使い方をすることが、ストレスからくる視力低下への対抗策でもあるわけですね。
最後にもう1つ、心理的なストレスへの対処法を知っておくのも、大切なことです。
もし、普段の生活の中で、お子さんがストレスを感じているのに気づいたら…
『子どものストレス 気づいたとき、気づくためにすべきこと』という特集(ウェブサイト「gooベビー」内)で、臨床心理士・学校カウンセラーの竹中麻理子さんは、「これってストレスかな?」と気づいたとき、親ができることとして次のような点を挙げています。
- おいしく楽しい食事の場をつくること
- 運動、入浴、そしてリラックスした睡眠を与えること
- 叱り方や指示のしかたを変えてみること
- 子どもの「いい部分」に着目して子どもにも伝えてあげること
- 外に出て、子どもといっしょに遊ぶ時間をつくること
竹中さんは、こういったことに気を配ることで「子どもが自分でストレスをコントロールする力をつけることにもつながる」としています。
子供にとって、ストレスに対処できる力を養うためには、普段の生活がモノを言う――と言えるでしょう。
まとめ
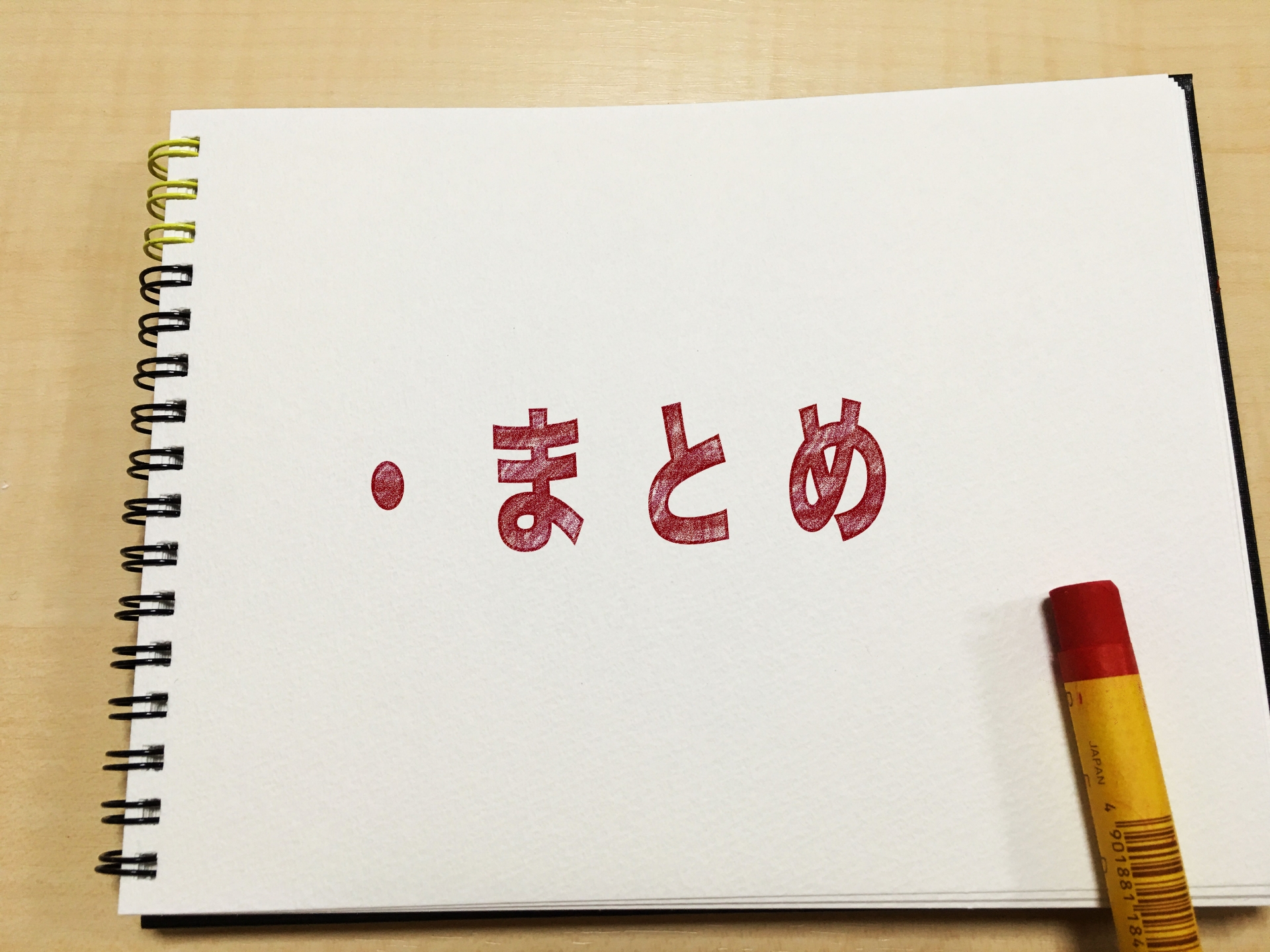
ストレスと近視には密接な関係があった
⇒誰にでも当てはまりそうな身近なストレスが、視力低下の原因となる可能性アリ!
ストレスをすべて排除するのは無理
⇒大事なのは、【ストレスに強く近視になりにくい目を養うこと】
そのカギを握っているのは…【目の使い方】
心理的なストレスへの対処法を知っておくことも大切
⇒子どものストレスに気づいたら…
- おいしく楽しい食事の場をつくる
- 運動、入浴、そしてリラックスした睡眠を与える
- 叱り方や指示のしかたを変えてみる
- 子どもの「いい部分」に着目して子どもにも伝えてあげる
- 外に出て、子どもといっしょに遊ぶ時間をつくる
などを実践することで、子ども自身がストレスに対処できる力を養う。
ストレスと近視がこんなに深く関わっていたなんて、ビックリ…
うちの子もストレスを感じてる?!
だったら、どこを改善すべき…?
「早期発見/早期対処」の機会を逃さないために…
視力ランドでは、無料で視力向上可能性判定を実施しております。
フォームに必要事項を入力するだけで、その場で瞬時に可能性を判定します。
お気軽にご利用下さい!
視力回復辞典(視力回復の真実)
おすすめタグ
人気記事ランキング

子どもの近視が将来の眼病につながる?──家庭でできるリスクを減らす対策

目は一生の資産——3分で整えるピント調節 “ピントフレッシュ”のすすめ

学校の視力検査A判定でも油断禁物—近視予防と『ホームワック』活用ガイド

自宅でできる視力回復トレーニング方法を徹底解説

スマホが原因で斜視に?増える”スマホ斜視”とその対策
関連記事

子どもの近視が将来の眼病につながる?──家庭でできるリスクを減らす対策

目は一生の資産——3分で整えるピント調節 “ピントフレッシュ”のすすめ

学校の視力検査A判定でも油断禁物—近視予防と『ホームワック』活用ガイド

自宅でできる視力回復トレーニング方法を徹底解説

スマホが原因で斜視に?増える”スマホ斜視”とその対策

眼科のワックは効果がないって本当?

ホームワックは効果なし?近視は本当に良くなるの?

学校検眼で「近視」と言われたら──できることから、始めてみませんか?